会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
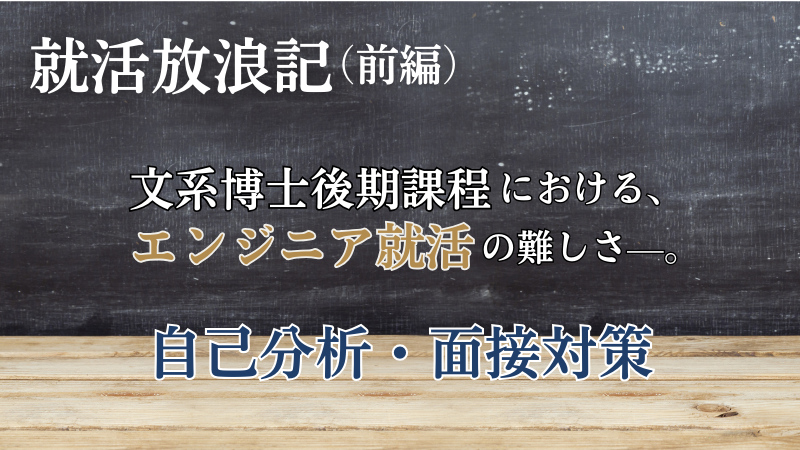
こんにちは。私は某私立大学の文系大学院博士後期課程で研究を行っている一般的な文系ドクターです(学部は理系なので一般的かどうかは微妙です...)。今回は、私のエンジニア就活体験について、徒然なるままに書き綴っていきたいと思います。内定をいただいたのは3社で、そのうち金融系企業に内定承諾をしました。
このコラムでは、3回に分けて徹底的に私の就活の棚卸しと解説をしていきます。特に 自己分析・就活の流れ(タイムスケジュール)・内定獲得から承諾の3点 については、ぜひ博士課程の皆様に参考にしていただければと思います。
「何がなんでも大企業!」はやめた方がいい
私自身、修士課程在学中の就活で、「大企業・有名企業に入りたい」という一方的な思いにとらわれました。コロナ禍の影響もあり、食品、エンタメ、出版、ITなど幅広い業界に応募したのですが、ほとんどがES落ち、面接の結果も散々で、大きな失敗を経験しました。
その反省を踏まえて、「何がなんでも大企業!」ではなく、自分にマッチした企業を選ぶため、特定のドメイン(事業領域)に絞りすぎず、エンジニアとして働きたいという前提で、以下の点に注意して就活を進めました。
※これらは、あくまで私が就活を通して感じたこと、考えたことです。
企業の謳い文句をそのまま受け取らない
まず、 「厳しい競争環境で圧倒的成長」 というキャッチコピーに惑わされないことです。実際には、部下と上司、同僚など、その環境ではまともなコミュニケーションが取れないという言葉の言い換えのこともあります。面接の際にもその雰囲気を感じとることがあります。
また、 「短期間(1年程度)でリーダーに昇格」 と謳われる企業についても、実情は厳しく、しっかりとした教育体制は整っておらず、指揮系統も未成熟で、自力で成果を出す努力が求められる、という場合もあります。
背景・理由をしっかり分析する
そして、よくあるのが 「業界シェアNo.1」 という言葉を使う企業です。この評価をそのまま受け入れるのではなく、なぜその地位にあるのか、その背景や理由を十分に理解することが重要です。例えば該当する業界において、最初期からその業界を引っ張ってきたリーディングカンパニーとしての意味か、競合他社が多いものの独自の技術などによって差別化を図っているのか、あるいは参入障壁が高くライバルが少ないため、独占・寡占状態であるが故のNo.1なのか、といったような様々なNo.1があります。
この違いによって、ノウハウの蓄積や、スキルの汎用性や将来性、企業(≒業界全体)の中長期的な成長といった部分に大きく関わるので、企業説明会などでしっかりと話を聞いた方がいいです。もちろん企業によっては様々な事業にチャレンジしているところもあるため、収益構造はしっかり把握するべきです。
「院生を積極的に採用しています」とは基本「理系修士」を指す
少し数字の話をします。令和5年1月、文部科学省 科学技術・学術政策局人材政策課が発表した『博士後期課程修了者の進路について』の資料によれば、令和3年度において博士後期課程修了者は約16000人います(修士課程修了者は71000人程度です)。そのうち約5,400人が民間企業へ就職しており、その内訳は研究開発職が約3,200人、その他の一般的な就職はたったの約2,200人となっています。
この数字が意味するところは、博士後期課程修了者の進路は大多数の「大学等教員やポスドク、研究開発職等で研究を継続する」か、少数の「研究をやめる」かという二大軸に大別されていることを示しており、進路を決める際にはどちらの道を選ぶのか、しっかりと自分自身で判断する必要があると強く示唆しています。自分は大学院進学時点で、研究職ではない民間企業への就職を決めていました。
文系院生は圧倒的に少数派
企業が 「院生を積極的に採用しています」 と謳う場合、その「院生」とは主に理系の修士課程修了者を指すことが多いのが現実です。そのため、同じ「院生」という言葉が使われていても、文系出身者に対しては同等の評価が与えられにくく、相対的に低く評価される傾向があります。
もちろん文系の学生は理系の学生と比較して絶対的な勉強量が少ないため、そのような評価は仕方がないのですが、この点にも注意しながら、就職活動の際は自分の強みやキャリアプランをしっかりと見極めることが求められます。企業説明会の際に気になったことは、どんなに細かいことでもどんどん聞いておくといいです。
企業は、 「採用する人材は企業が必要とする人材像に合っていればよく、必ずしも博士号を持っている必要はない」 との理由で博士課程修了者の採用をしません。つまり、長い年月をかけて得た博士号が、場合によっては単なるムダ(「足裏の米粒」と言われます)のように扱われる可能性があるということです。
自己分析は死ぬ気でやろう
就活をうまく進めるためには、自己分析は死ぬ気で行うべきです。大学院生であれば、研究内容について説明できることは当然のことですが、面接は専門家向けの研究発表の場ではなく、あくまで自分の価値を伝えるための機会です。
たとえば、 「なぜ博士後期課程に進学したのか」 や 「年齢が高い」 といった否定型質問に対しては、単なる説明ではなく、自分の決断に至った背景やその意義をしっかりと整理し、言い返せる準備をしておくことが重要です。
実際のところ、日本社会や日本企業では、学歴(すなわち大学名)といった表面的な評価が依然として大きなウェイトを占めています。多くの場合、実際にどのような価値を提供できるかという点よりも、名門大学出身かどうか、または学歴そのものが採用の重要な判断材料となります。特にエンジニアは「仕様通りに開発できる人材」としての価値を評価したいという企業が多いですが、そうした固定観念を打破するためにも、自分自身の強みやスキルを深く理解し、明確にアピールできるようにする必要があります。
自己分析のフレームワーク
ここからは自己分析のためのフレームワークについて述べていきたいと思います。エントリーシート作成にも生かせるものですが、主に面接対策を軸として書いていきます。
一般的な分析:熱意と能力
一次面接→二次面接→最終面接、となっている場合、一次面接では人事担当、二次面接ではチームリーダー・マネージャーなどの特定の部門責任者(CTOやCPOが来る場合も)、最終面接では役職(副社長等)が相手になります。正直、二次面接が一番厳しいです。
この時人事が評価するのは 熱意 、責任者が評価するのは 能力 、役職が評価するのは 長期的に働いて成果を出してくれるか 、といったようにある程度分かれています。そのため必然的に二次面接が厳しくなってしまいます。面接の各段階において質問の内容や目的が大きく異なるため、それぞれに合った対策が必要になります。
二次面接以降は一次面接などで得られたデータなどに基づいて変わった質問をぶつけてくることもありますが、そこに関しては後ほど説明します。
【自己紹介】
(1分以内):最低限、名前・所属・ 研究内容 について述べること。長々と喋る必要はありません。
【経歴 (大学を選んだ理由)】
どこの大学出身か、なぜその大学・学部・学科を選んだのか。その大学を選んでよかったか。→ 高校までの経験や考え方など、ちゃんと思い出しておくこと。自分は滑り止めの大学だったので、希望通りの結果ではなかったが、大学に入って友達とプログラミングの勉強をしたり、数学を教え合ったりした経験が役に立った、ということを述べました。
【経歴 (大学院へ進学した理由)】
なぜ大学院へ進学したのか。 大学・大学院ではどのようなことを学んだのか、それがどのように生かされているか。特に 博士後期課程への進学理由 は明確にする必要があります。→ 卒論(卒業研究)内容や修士論文の内容についても聞かれることが多いため、簡潔に答えられるようになっておくこと。進学理由は「もっと勉強したかったから」でも十分かもしれないが、じゃあ進学してみてどうだったの?という質問にも答えられるようにしておきましょう。
※修士課程までであれば「2年間頑張ったね、社会人として頑張ろうね」と評価されますが、博士後期課程になってしまうと、生半可な評価がもらえないです。ほとんどの会社は「新卒採用だから即戦力じゃないけど」って感じの面接になるので、気を強く持って臨みましょう。(そういうスタンスを取る会社を選ばないというのも戦略です)
【研究】
現在の研究内容、進捗、成果について、 早口にならないよう落ち着いて論理的に順序立てて 説明しましょう。博士後期課程の学生である以上、面接における研究に関する質問のウェイトが必然的に大きくなります。学会発表ではないし、専門用語をベラベラと喋る場でもありません。成果に至ったプロセスも重要ですが、ドクターの学生であれば成果があるはずなので、論文を出していたらそのテーマで話すでも可です。
研究について大幅に補足すると、二次面接ではより研究について深掘りされ、しっかりとした確認やツッコミがくるので注意が必要です。先の内容に加えて、研究をしている 理由や意義 に関する質問、研究の やりがい 、 面白い/楽しい 部分、 苦労 した点や 工夫 した点、 困難をどのように乗り越えたか 、あなたの研究や専門性が 社会にとってどのように役立つ のか、 研究を通して身につけた能力や姿勢、考え方はどのようなものか 、についての質問がくるので準備が必要です。
大学生活 :どういった「特徴的な」大学生活を送ったか、相手が理解できるレベルで説明しましょう。基本的にはサークルやバイト、留学の経験がおすすめです。 院生であれば学会発表(特に理系だと「〇〇賞」的なものがもらえる。文系だと難しいかも)などでも色付けできるのでOKです。 長期留学じゃなくても、短期留学の際に社会人と知り合って仕事での英語の重要性が身に沁みた、とか現地の方と話すことができて英語でのコミュニケーション能力が向上した、でも十分ウケがいいです。
【周囲からどのような人だと思われているか】
例えば同級生などからどのような人だと思われているかを客観的に述べましょう。直接的に言われていなくても、なんとなくで全然OK。 この人エンジニアに向いてるのかな? という部分にも関わってくるので、ポジティブな部分に焦点を当てましょう。
【失敗経験】
とても大事です。どのような失敗をしてしまったか、その失敗をどのように分析したか、それを乗り越えるためにどのような行動を起こしたか、現在はその失敗経験をどのように考えているか、といったように自身の失敗を多角的に分析しておく必要があります。自分は大学院を辞めた経験と、生徒会での経験、そして以下にあるようにインターン経験の三刀流でなんとかやりくりしました。とりあえず失敗談はたくさんストックしておきましょう。
【長所と短所】
失敗経験に関連して、自分の長所と短所、強みと弱みを把握しておくことが大事です。表裏一体型にしておくと対策しやすいと思います。 「考えるより行動することが強み」←→「物事のプライオリティをつけるのが苦手、新しいものに飛びついてしまう」 みたいな感じにしておくと、短所をどのようにカバーするか説明しやすいです。
【インターン経験】
一番大事です。1週間程度の短いやつでもなんでもいいので経験しておくべきです。自分は大学2年の時に行った防衛省のインターントークを使い回したので、「(面白いけど)こいつまたこの話してるよ」的な雰囲気になりましたが、 スルメ戦法(相手からの質問→それに適した成功・失敗経験→改善点→現在の自分の考え方や働き方への反映→相手の質問への回答→次の質問→…) で戦い抜きました。
ここの内容を固めておくだけで、一次面接は余裕で乗り越えられるといっても過言ではないです。
【事業理解】
自分が面接を受ける会社についてどの程度理解しているか、なぜその会社に入社したいのか、明確にしておくことが大事です。会社のホームページ内の 企業情報や事業内容、投資家向けのIR(Investor Relations)、社員が書いたブログ、エンジニアであれば技術ブログやテクニカルレポート など、ヒントになるものはいっぱいあるので必ず確認しましょう。人事の方から「ここ確認しておいてね」と教えていただける場合もあります。自社プロダクトがある会社は特に重要です。
【将来像】
どのような社会人になりたいか、どの事業に参加したいか、どのように成長したいか、あなたの経験をどのように仕事に活かしたいのか、自分が思い描く理想の社会人像を具体的に把握して言語化できるようにしておくことが大事です。
その他追加情報:zoomやteamsなどを用いたオンライン面接の場合、「画面映え」も意外と重要です。画角チェックやカメラ目線を意識すること、背景はできるだけ綺麗なもの(バーチャル背景を使用)、明るさの調節、イヤホン推奨など、綺麗な環境で面接を受けましょう。カンペは用いず、話すときは笑顔で、相手の話を聞くときのアクション(頷く)や姿勢も意識して、少し大袈裟でもいいので取るべきです。
エンジニア特化型分析:技術理解と開発経験
IT業界やそれに関わる仕事を志望する理由:
一次面接レベルの質問です。受け身の理由は印象が悪いので、自発的に、主体的に志望理由を構築することが大事です。「周囲が〇〇だから…」「××と言われたから…」といったようなものは御法度です。ドクターであればやっぱり現在の研究と結びつけて述べるべきです。就活の軸を明確にしておきましょう。
研究で身につけた姿勢や考え方を”エンジニアとして”どのように生かしていきたいか :
一次面接レベルの質問です。技術ももちろん大切ですが、エンジニアとして働いていく熱意はありますか、それを裏付けできる研究への取り組みが知りたい項目です。
プログラミングの学習経験、どのような言語が使えるか、勉強方法 :
この質問に対する回答は絶対に押さえましょう。CだろうがjavaだろうがPythonだろうが、いつからどれくらい使っているかを説明できるようにする必要があります。大学の授業で習った、自分で色々作ってみた、研究で使ったなど、「できることはできる」とアピールすることが大切です。
あなたの研究における技術的な側面(使用している技術)を説明できるか :
技術は好きですか、ちゃんと理解して使っていますか、という質問に近い感覚です。面接という短い時間で研究で使用している技術を全て説明するのは不可能なので、ここぞという時に専門的な質問に対し、明確な説明ができるように準備しておきましょう。
(本格的な)開発経験はあるか :
新卒採用なので、ないなら「ない」といってもそこまでマイナスイメージはない、と考えていいです。できないことをできる、と言う必要はないです。ただし、「エンジニア志望なのに技術に興味ないの?」と思われないように、今はまだコードをバリバリ書くような生活ではない、ということを一言付け加えておけば全然OKです。
クラウドを知っていますか?クラウドでの開発はできますか? :
この質問がかなり多かったです。アプリ開発等のみならず、オンプレミス(自社運用/社内サーバーを構築して運用)からクラウド(インターネット上でシステム運用)に切り替える、であったり、開発環境がクラウドに依存している会社が多い印象です。興味ないね、とか言っている場合ではないです。
「チームで何か成し遂げた経験はありますか?その時の役割は?」 :
主体性と協調性、コミュニケーション能力の評価につながるものです。特に多くの場合エンジニアはチームで開発するので、適性があるかを確認したいという意図があります。文系だと理系と異なり単独で研究を行うことが多く、研究室に集まって研究しようぜ!的なムーブはないので、アピールしにくい印象です。自分はインターンの話を使い回してここは乗り切りました。
「どのようなエンジニアになりたいですか?」 :
先述の将来像とは異なり、いわゆるスペシャリストに進みたいのか、ジェネラリスト(マネジメント)に進みたいのかの質問です。技術が大好きでって人はスペシャリストを目指すべきでしょう。先の失敗体験とかインターン経験を踏まえて話すことが大事です。
自分はチャットボット開発の研究をしているので、サービスや製品の利用者(エンドユーザー)の声がエンジニアまでしっかりと届く風通しのいい環境、社内分業などにより固定化されたヒエラルキーがなく、柔軟に働くことができる環境がいい、ということは主張しました。
これにより、顧客の声を生かした開発ができる(フルスタック)エンジニアになりたい、と述べたました。
「なんでエンジニア?コンサルとかデータサイエンティストじゃなくていいの?」 :
院生にはコンサルの給料がいいので大人気、最近だとデータサイエンティストも人気急上昇なのに、なぜわざわざエンジニアになりたいのか、という質問はあらゆるところで聞かれました。
ちゃんと開発がしたい気持ちが強かったのと、データサイエンティストはどうかな…って感じがしたので、エンジニア一本に絞って就活しました。
【逆質問】
とても大事です。以下の質問は面接官に刺さった感じがあった質問内容です。アドリブだと難しいので、先にある程度固めておいた方がいいです。
1.ユーザーからのフィードバックを製品・プロダクトの改善においてどのように反映させるか。
ここで「会社が決めたことをやるだけ」「金にならないことはやらない」 しか言えないエンジニアは、個人的に合わないと考えていました。
1’.自分が想定していないフィードバックが返ってきた場合はどのように捉えるべきか。
1に関連してする質問。相手に質問を投げっぱなしにしないで、ちゃんとキャッチボールをすること。
2.非言語コミュニケーションについての考え方や製品における将来性
テキストベースでのコミュニケーションでは限界があります(自分の研究で扱っている部分です)。マルチモーダル的思想もちゃんとあるか気になりました。エンジニアはコミュニケーション苦手な人が多そうなので聞いてみました。
3.生成AIについての考え方や業務での導入や活用、製品の展開
AIとか生成AIなんてまだまだ先だねぇ、という感じの企業がほとんどでした。「そういうのは我々(エンジニア)が考えることではない」的な人も多かった印象です。
4.リーダーの考え方:ボトムアップorトップダウン、これらを使い分けるための社員の能力を見極めるにはどうすればいいか
ここは企業によって異なる答えが得られて面白かったです。特にエンジニアという「個」の強い集まりにおける組織の考え方が聞けて面白かったです。
評価の悪い逆質問として、後日人事の方から言われたのは「福利厚生は充実していますか?」とか「残業はありますか?」とか「転勤はありますか?」はダメらしいです。こういった質問をした人は、コードが書けてエンジニアとしての能力・適性が高くても落としました、と教えていただきました。
ここまでがエントリーシートの作成や、面接対策で役立つ内容になります。ぜひ参考にしてください。次回は就活の流れ・スケジュールについて説明します。
(中編へ続く...)
会員登録すると
このコラムを保存して
いつでも見返せます
マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事
P&G アクセンチュア
内定攻略 会員限定公開
トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム
この記事を友達に教える



