会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
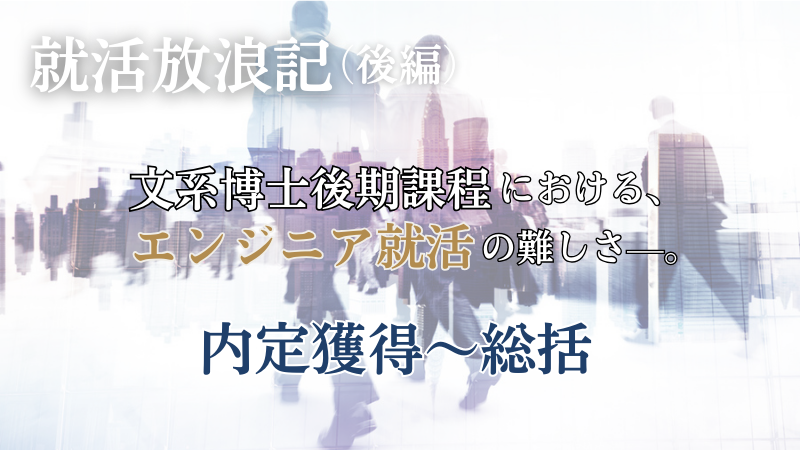
こんにちは。私は某私立大学の文系大学院博士後期課程で研究を行っている、文系ドクターです。私はエンジニアで就活し、内定をいただいた3社のうちの金融系企業に就職します。
前編では就活における自己分析・面接対策を、中編では就活開始から最終面接までのフェーズについて書いてきました。
後編の今回は、完結編として内定獲得から就活の総括までを綴っていこうと思います。最後までお読みいただければ嬉しいです。
(前編はこちら)
(中編はこちら)
D2/ 12月:内定獲得
学会行脚からの最終面接 突貫スケジュール
12月の1週目にしてよーやっと内定が出ました。12月上旬から中旬にかけて3週連続で3件の学会報告(東京→広島(2泊3日)→東京→フランクフルト(ドイツ)→ウィーン(オーストリア)→ブルノ(チェコ)(4泊5日)→ウィーン→フランクフルト(1泊)→ロストバゲージ→東京)があったため、精神的にも肉体的にもギリギリでしたが、なんとかなりました。
スーツケースが破損した際に、チェコのホテルで修理用のテープやハサミを貸していただけてとても助かりました。今度は首都プラハや温泉保養地カルロヴィ・ヴァリにも行ってみたいです。フランクフルトからの帰国後、3日間で4社連続(1日に2社受けた日を含む)で最終面接でした。その後体調を崩しました。
最終面接までに起きたトリッキーな面接として、「2種類のプログラミング言語の仕様の違いについて説明してください」であったり、「これからブレーンストーミングを始めます。我が社の業務内容であなたが興味があるものを一つ挙げ、それについてどのように貢献できるか、もしうまくいかなかった場合には、どのように打開策を考えられるか述べてください」であったり、「まず最初にあなたから質問してください」といったものもありました。
全ての会社がこのような面接を行うわけではないです。「追い詰められた時こそ火事場の馬鹿力が発揮される」的な思想があるらしいので、キラーフレーズは隠し持っておいた方がいいです。
3社の内定を獲得
結果として内定については3社、最終面接で落とちたのは2社でした。最終面接と言ってもこれまでの面接(主に二次面接)と大幅に変わったことは起こりません。少し違うのが入社意思を確認されたり、志望順位を聞かれたりと内定を出す・出さないを見極めたい、という質問が多くみられました。1社は実際にオフィスで面接を行い、社内の雰囲気や空気も知ることができてよかったです(みなさんちゃんと挨拶してくださって嬉しかったです)。面接後にメンターとの面談がある会社もありました。
これらの結果及びフィードバックを含めて、内定承諾を決めた理由を次に書きたいと思います。12月の最終週(クリスマス周辺)になると、企業側も忙しくほとんど連絡が取れなくなったため、詳細な連絡は翌年1月になりました。
この時期の研究としては、忙しすぎてほぼ進捗はなかったのですが、学会報告の際にいただいた意見などを集約し、論文の下書きをしたり来年以降発表する必要のある学会の選定などを行っていました。
D2/ 1月:内定承諾
最終落ちの2社
ここからは内定をいただいた会社のうちどこに内定承諾を出すか、を考えるフェーズになります。本格的な就活は終わりです。1月末までのA社プレミアムスカウト企業数は34社、外資就活ドットコムスカウト企業数は26社の計60社でした。
(説明会・カジュアル面談に25社くらい参加して、そのうち15社くらいにエントリーしました。エントリーから一次面接+適正検査にかけて落ちたのが10社程度で、二次面接で落ちたのは1社のみ、というスケール感です。)
まず落ちた会社のフィードバックとして、1社(アドテク系)は「新卒としては落ち着いている」「PM(プロジェクトマネージャー)の方が向いてそう」というのがありました。そもそも将来的にはPMも目指していきたい、というのは1次面接の時点でも述べているので、わざわざ最終面接まで進めておいてご丁寧に落とすのは、ヘタなお笑いみたいでした。最終面接時に「そんな就活生1人1人に時間かけてらんないよ」と言われたので、こちらの話はあまり聞いてなさそうでした。
もう1社(アドテク系)からは、「非常に多くの内定者の意思決定に時間を要している」「熱意やスキルについては高く評価し、感謝している」という丁寧な落とすよ〜メールが送られてきました。後日送られてきたフィードバックについては、口外しないでほしいとの連絡がありました。面接の感じは悪くなかったのですが、何を考えているのかよく分からない企業でした。
内定先のフィードバック
内定を頂いた3社についても書いていきたいと思います。私が入社を決めた企業(金融系)の最終面接官からの評価は以下のようになっていました。
- 自らの経験を通じてしっかりと自尊心を芽生えさせており、同年代に比べても成熟度は高い印象
- 受け答えがスムーズで理路整然としている
- モチベーションの源泉はことを成すよりも、貢献実感のタイプに見えた
- 総じて誠実でチームでの協業にも適用できそう。カルチャーフィット度合いも高そう
- わかりやすいロールモデルがいると、成長スピードが上がりそう
このフィードバックは正直すごいなと感心してしまいました。複数回の面接を通じて評価軸が私という人間のこれまでの経験や指向性、そして将来的なキャリアビジョンまでを勘案し、企業の組織文化とのマッチングを図るため、自分に合わせた評価をしてくださっていたことに驚きました。また、他企業とは異なり日本語で適切な距離感のコミュニケーションがとれる人が多かったことと、修士の時に金融分野の内容を齧っており事業内容が面白そうだったため、こちらの企業に内定承諾しました。
他の2社についてもちゃんと「断った」理由があります。まずG社(不動産系)については、最終面接までを含めたフィードバックをいただいた際に、「研究」と「不動産」という2つの大きな軸に基づいて評価していただいたことがわかりました。
私のことをfunnyな(面白い)人と評価していただけました(もちろんポジティブな意味でのfunnyです)。しかし、詳細を聞いたところ、研究については私の研究分野が独自のものであるため、評価が難しかったこと、また「不動産への興味」という部分についても判断が難しいとのことだったため、入社後にミスマッチが起こる可能性を感じ辞退しました。
私の卒論ゼミ(応用数学系・解析学メイン)でも「都市の発展シミュレーション」や「コンビニエンスストアの出店計画シミュレーション」、「建物内での音声の反響シミュレーション」といったように、不動産関係の研究をしていた人も多くいたので、彼ら/彼女らのように不動産に明確に興味があるか、と問われると難しい部分があったので辞退しました。でもすごいいい企業だったなぁ…。
最後にもう一社のD社(会計系)についてです。この会社は初任給などの条件がとても良かったのですが、言葉の端々に圧力をかけるような話し方をする面接官ばかりで精神的にとても疲れました。また入社後3ヶ月以内に2つの資格を取る必要があるにも関わらず、そのような説明を面接中に一切行わなかったため、情報をオープンにしないという性格に対しても不信感が生じました。人事の方に確認した際には、社内でも同様のコミュニケーション様式である、とのことで辞退しました。「上司や部下に関わらず正面からぶつかり合ういい会社だ」と言っていましたが、要はまともにコミュニケーションとれてないんだろうな、という雰囲気を感じました。
以上でどのように内定承諾を考えるべきかについてまとめました。自分は評価軸のすり合わせと透明性が重要だと感じました。
【総括】これから就活を始める文系ドクターへ
ここからは文系ドクターに焦点を絞って短く書いていきたいと思います。
「呪い」を解こう
おそらく文系の博士後期課程に進学した人はほぼ全員 「研究の世界でしか生きられない」、「研究から逃げるのは甘え・間違い」、「ここまで来たら研究者になるしかない」 という謎の圧力で動いていると思います。大学院進学時に思い描いていたような生活を送ることができず、研究成果は思ったより出ず、論文を書くためにテーマを何度も変更し、研究が思ったより楽しいわけでもない、卒業後はどうしようという鬱屈とした不安がある、という人が大半のはずです。
正直な話、研究者になれるのは金持ちの家に生まれ、両親や周囲の人に助けられ、いつでもテストの点数は良く、いい学校に進学し、受験に成功し、東大卒・京大卒などのエリートコースを踏み外すことなく、大学院まで含めて20年以上箱庭で運よく”蝶よ花よ”と丁寧に育ててもらった人です。今更このような人たちと競い合っても、ハナから無駄です。「東大限定で教員の公募が来る」というのも当たり前の世界だからです。
今は研究という特定の領域の狭い世界で自分の価値を相対的に上げていくことに必死かもしれません。しかし、自分は就活を通して、自己分析のみならず、様々な価値観や哲学を持つエンジニアと研究について話し合うことができ(面接という短い時間であっても)、より「自分の持つ絶対的な価値」と「自分の進めてきた研究の価値」の理解を深めることができました。
これは研究の世界の住人である研究者とのやりとりでは絶対に辿り着けなかった場所です。 文系ドクターという日本社会で価値の低い人たちがいかに生き残るかを考えるには、就活というのは最後のチャンスだと思います。
社会は変わる、大学は変わらない
自分は大学院で2年間TAとして、2年間(3年目も継続が決まりました)大学助手として勤務してきましたが、結論として大学は変わりません。もちろんほんの少し仕様が変わっているものもありますが、ドラスティックに変わることを期待するだけ無駄です。
しかし大学の意思に関わらず社会は変化します。楽天インサイトが独自に構築した「イノベーター分類手法」に基づき、生活者を5つのセグメントに分類し理解するソリューション(*外部サイトに遷移します)によれば、新しいものを進んで採用する2.5%のイノベーターや、オピニオンリーダーとしての13.5%のアーリーアダプターが初期市場を形成します。
一方でそれらとは対照的にイノベーションが伝統化するまで手を出さない16%のラガードと呼ばれる人々もいます。大学が社会に送り出す必要があるのは、イノベーターやアーリーアダプターであるにも関わらず、大学そのものが研究者というラガード層で固まっていては意味がありません。なぜ日本の研究者=ラガードと言い切れるかというと、私が書いた新規性のあるテーマの人工知能関連の論文を読んで連絡してきたのは、アメリカと中国とヨーロッパであり、日本からは一切なんの連絡もないからです。
社会で求められる人材が変わっていく以上、大学側も変わるべきなのですが、残念ながら大学が変わることはありません。そのため、通過儀礼としての価値をもつ就活に取り組む、というのは無駄ではないと言えます。
文系であることの強みを活かした就活を
文系であることは、弁護士などの資格を持っている場合は別ですが、社会で働くにあたり強みにはならない、というのが本音です。最初から理系の学部・学科を選ぶべきです。しかし、長所と短所の部分で書いたように、それらは表裏一体として捉えるべきです。
文系であること自体が直接的な強みと認識されにくい現実は否めませんが、その反面、文系ドクターならではの柔軟な思考や広い視野、そして情報を多角的に捉える力は、企業にとっても貴重な資質となり得ます。例えば、複雑な社会問題や人間関係、組織内のコミュニケーションにおいて、文系ドクターの鋭い洞察力や独自の発想は、技術のみでは補えない新しい価値を生み出す可能性があります。
また、大学院で培ったリテラシーや分析力は、単なる知識の暗記や技術的スキル以上に、戦略的な意思決定や企画力、さらには対人コミュニケーションの面でも大いに役立ちます。つまり、一見弱みと捉えられがちな部分も、実は状況や環境に応じて十分な強みへと転換できるのです。
このように、自分自身の文系ドクターの特性を正確に把握し、それをどのように企業や職場での具体的な価値に結びつけるかを戦略的にアピールすることが、文系ドクターが就活を成功させるための鍵となります。自らの短所とされる点も、状況に応じたアプローチ次第で強みとなり得ます。
会員登録すると
このコラムを保存して
いつでも見返せます
マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事
P&G アクセンチュア
内定攻略 会員限定公開
トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム
この記事を友達に教える



