会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
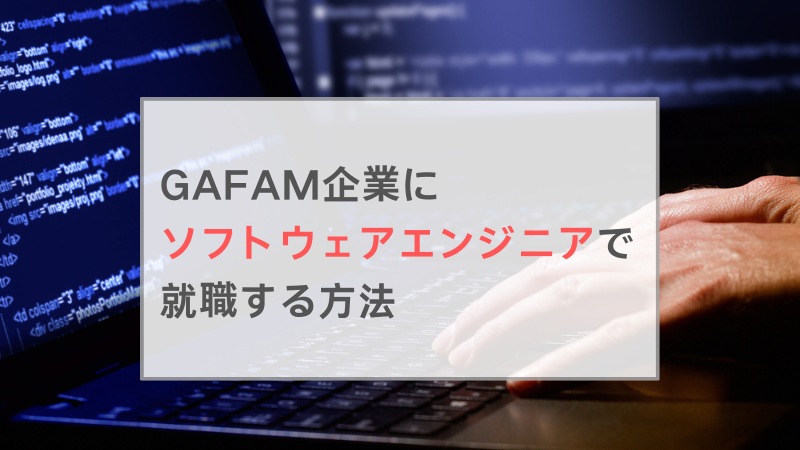
皆さんは難関外資系企業といえば、まずどのような企業を連想するでしょうか。例えば戦略コンサルや投資銀行、外資系メーカーなどが挙げられると思いますが、近年はそれらだけではなく、Google、Apple、MicrosoftといったグローバルIT企業のエンジニア職の人気も急上昇しており、狭き門と言われています。
そもそもこれらの企業は、東大・京大の大学院の中でも情報系の学生や海外大生など一部の学生にしか採用募集が公開されなかったり、採用人数が非常に少なかったりすることもあり、なかなか選考の実態を知ることができません。
また、他の職種・企業の新卒採用のように「経験不問」というわけにはいかず、 高度なプログラミング能力や経験が選考の時点から求められているのが「外資系IT企業でのエンジニア職」というキャリアです。
今回は、そんな外資系IT企業にエンジニアとして新卒入社するための方法について、ご紹介致します。最先端テクノロジーを自ら生み出していくエキサイティングな現場で、自分のスキルを発揮していくというキャリアパスに少しでも興味のある方は、ぜひご覧下さい。
【関連コラム】
・GAFAMにソフトウェアエンジニアで内定。「世界トップレベルの技術、人に関われるチャンス。デメリットなしでリターンは大きい」
・“普通の人”がGoogleのソフトウェアエンジニアになるには?採用ステップ、入社面接、評価ポイント、対策まとめ
・ソフトウェアエンジニア職志望のための面接過去問まとめ-技術面接編-
・ソフトウェアエンジニア職志望のための面接過去問まとめ-一般面接編-
・ソフトウェアエンジニアの面接で使える逆質問例文|何を聞けばいいのか?
・GAFAMにソフトウェアエンジニアで内定。「世界トップレベルの技術、人に関われるチャンス。デメリットなしでリターンは大きい」
・“普通の人”がGoogleのソフトウェアエンジニアになるには?採用ステップ、入社面接、評価ポイント、対策まとめ
・ソフトウェアエンジニア職志望のための面接過去問まとめ-技術面接編-
・ソフトウェアエンジニア職志望のための面接過去問まとめ-一般面接編-
・ソフトウェアエンジニアの面接で使える逆質問例文|何を聞けばいいのか?
【GAFAM企業の選考体験記】
・Google 22卒 本選考レポート
・Amazon 22卒 本選考レポート
・日本マイクロソフト/マイクロソフトディベロップメント 23卒 本選考レポート
・Google 25卒 インターンレポート
・Google 22卒 本選考レポート
・Amazon 22卒 本選考レポート
・日本マイクロソフト/マイクロソフトディベロップメント 23卒 本選考レポート
・Google 25卒 インターンレポート
【GAFAMのインタビュー記事】
・「グローバルプロダクトで大きなインパクトが与えられる」Amazonの新卒ソフトウェアエンジニアが語る、同社の魅力とは
・新卒でMicrosoft米国本社のSWEに「新しいチャレンジが多く、成長につながる」
・学部卒でGAFAMのソフトウェアエンジニアに内定「周囲より早く働き、社会的インパクトを与えたい」
・「グローバルプロダクトで大きなインパクトが与えられる」Amazonの新卒ソフトウェアエンジニアが語る、同社の魅力とは
・新卒でMicrosoft米国本社のSWEに「新しいチャレンジが多く、成長につながる」
・学部卒でGAFAMのソフトウェアエンジニアに内定「周囲より早く働き、社会的インパクトを与えたい」
GAFAMの新卒採用には、どのようなルートがあるのか?
基本的には以下の4パターンが挙げられます。
...
会員登録して全ての内容を見る
続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。
外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。
この記事を友達に教える



