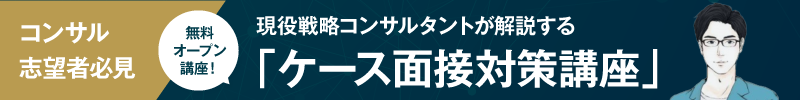【戦略コンサル内定】戦略コンサルタントの仕事内容とは?|業務内容や魅力
2024/09/17
会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます

意外と知らない?戦略コンサルタントの業務内容
こんにちは。外資就活 コンサルチームです。
このコラムでは上位学生に最も人気の高い業界の一つである 「戦略コンサルティング業界」 について、その仕事内容を詳しく説明していきます。
具体的には、
・戦略コンサルの主要業務
・戦略コンサルに必要なスキル
・戦略コンサルの仕事の進め方
・戦略コンサルの魅力
・戦略コンサルの年収
についてご紹介します。
戦略コンサルに少しでも興味のある方は、まずこのコラムを読み仕事内容のイメージをつかみましょう。また現時点では興味のない方も、志望業界の選択肢を広げるという意味でぜひご一読ください。
下記にキャリアパスや職位などについてまとめた戦略コンサル内定への道シリーズのコラムを掲載しているので、戦略コンサルに興味のある方はぜひチェックしてみて下さい。
・【戦略コンサル内定】コンサルタントの役職一覧|仕事内容や若手の働き方、転職先
・【戦略コンサル内定】戦略コンサル早期内定を目指す選考対策スケジュール
・【戦略コンサル内定】Webテスト対策まとめ|SPI・TG-WEB・玉手箱・独自形式
・【戦略コンサル内定】ケース面接対策とは?練習方法や対策の仕方について|初級編
・【戦略コンサル内定】ケース面接の面接対策!例題28問と解説|中級編
・【戦略コンサル内定】各社戦略コンサルティングファームの過去問と出題傾向|上級編~McK・BCG・Bain・Kearney・S&・RB・ADL・ZS・DI・IGPI・CDI・AC~
・A.T.カーニーのES(エントリーシート)・体験記一覧
・ベイン・アンド・カンパニーのES(エントリーシート)・体験記一覧
・マッキンゼー・アンド・カンパニーのES(エントリーシート)・体験記一覧
・ボストンコンサルティンググループのES(エントリーシート)・体験記一覧
戦略コンサルの主要業務は「戦略立案」「DD」「オペレーション支援」の3つ
戦略コンサルの仕事は、企業の問題点の発見やさらなる成長戦略を外部から分析して提案を行うことであり、端的に言えば 「企業のお医者さん」 や 「企業の作戦参謀」 などと表現できるでしょう。具体的には主に、企業の経営戦略策定、買収の支援、コストの削減といったクライアントの希望を援助する業務に取り組んでいます。
その中でも、大手の戦略コンサルティングファームは、日本を代表するような大企業や政府機関をクライアントとして、クライアントが成長・状況回復するために必要な大きな意思決定を外部から補助しています。
戦略コンサルの主な仕事内容は、大きく分けて3つあります。
②DD(デュー・デリジェンス)
③オペレーション支援
戦略立案は想像に難くないと思いますが、一方でDDやオペレーション支援については聞きなれない方もいるのではないでしょうか。
では、これら3つの仕事内容について詳しく見ていきましょう。
①戦略立案|企業の経営戦略策定を行う
戦略立案とは、その名の通り クライアント企業の戦略を立案する 仕事です。中期経営計画の策定の手伝いをすることもあれば、「利益率の悪い事業部をどのようにして黒字化するか?」や、「○○事業に参入すべきか?(や新規事業立案)」などの難しい経営課題への解を、 3ヶ月から半年という短期間 で出すことが求められます。
答えのない問いについて考えることは、難易度が高い分やりがいを感じる人も多く、戦略コンサルの花形の仕事と言えるでしょう。一方で純粋な戦略案件というのは減少しつつあり、実行支援まで行うファームが増えてきています。
②DD(デュー・デリジェンス)|企業の価値を算定し買収の支援をする
DDとは、
...
会員登録して全ての内容を見る
続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。
外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。
この記事を友達に教える