会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
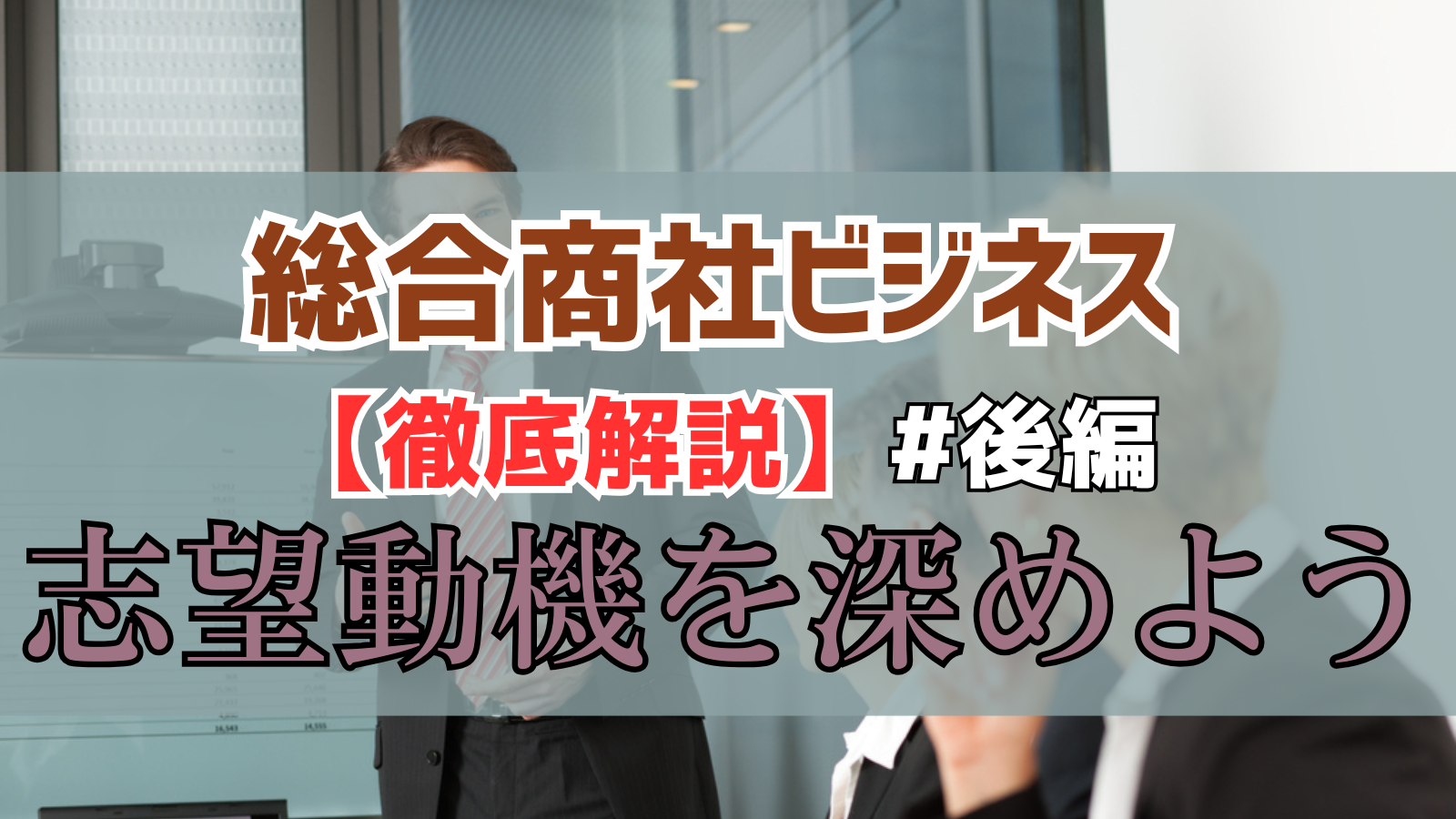
こんにちは、26卒で5大商から複数の内定を獲得した者です。今回は、前編・後編に分けて、商社のビジネスの仕組みを徹底的に解説しています。商社のビジネスを理解し、志望動機のブラッシュアップに活かしましょう。
この記事は、前編の続きとなります。資金調達や戦略、グローバル展開等について詳細に解説しておりますので、読み込んで理解に役立ててください。
前編記事はこちら
6.資金調達と金融機能
資金調達戦略の概要
総合商社は大規模な投資と運転資金需要を満たすため、多様な資金調達手段を活用している。高い信用格付けを背景として、資本市場と銀行借入の両方で有利な条件での資金調達が可能となっている。
格付けの維持・向上は資金調達コストに直結するため、各社とも財務健全性の維持を重視している。適切な財務レバレッジの管理、収益の安定性確保、リスク管理体制の強化などにより、格付け機関からの評価向上に努めている。
資金調達の通貨分散も重要な戦略である。円建て調達に加えて、米ドル、ユーロ、その他アジア通貨での調達を行うことで、為替リスクの軽減と調達コストの最適化を図っている。
調達期間の分散により、リファイナンスリスクの軽減も図っている。短期から長期まで、償還時期を分散させることで、特定時期の資金調達環境悪化の影響を最小化している。
社債発行による資金調達
総合商社の資金調達において、社債発行は重要な手段となっている。国内市場での円建て社債発行に加えて、海外市場での外貨建て社債発行も活発に行われている。
国内社債市場では、普通社債、劣後債、ハイブリッド証券など多様な商品を発行している。機関投資家の需要動向を踏まえて、発行タイミング、金利条件、発行規模を決定している。
海外社債市場では、ユーロ債市場、米国市場、アジア市場での発行を行っている。各市場の投資家ベースの特徴を活かして、最適な発行条件の実現を目指している。
ESG債券の発行も近年増加している。グリーンボンド、サステナビリティボンドなどの発行により、ESG投資を重視する投資家からの資金調達を行うとともに、サステナブル経営への取り組みをアピールしている。
銀行借入とシンジケートローン
銀行借入は総合商社の資金調達における重要な柱である。メガバンクとの長期的な取引関係を基盤として、安定的な資金調達を実現している。
コミットメントライン(融資枠)の設定により、必要時の機動的な資金調達を可能としている。通常時は未使用で待機させ、資金需要が発生した際に速やかに実行できる体制を整えている。
大型投資案件では、プロジェクトファイナンスやシンジケートローンを活用している。複数の金融機関で資金供給を分担することで、大規模な資金需要に対応するとともに、金融機関のリスク分散も図っている。
海外での資金調達では、現地金融機関との関係構築が重要である。現地通貨での資金調達により、為替リスクの軽減と現地での事業展開支援を実現している。
トレードファイナンス機能
総合商社の金融機能の中でも、トレードファイナンスは商社の競争力を支える重要な機能である。貿易取引に伴う様々な金融ニーズに対して、包括的なソリューションを提供している。
輸入代金立替(掛け払い) では、顧客企業の資金繰りを支援するため、商社が輸入代金を立て替えて、後日顧客から回収する仕組みを提供している。この機能により、顧客企業は資金負担なく輸入取引を実行できる。
信用状(L/C)の開設・確認 では、売り手と買い手の間の信用リスクを軽減するため、銀行保証付きの決済手段を提供している。特に新興国との取引や新規取引先との商談において重要な機能となっている。
為替ヘッジサービス では、顧客企業の外貨建て取引に伴う為替リスクを軽減するため、適切なヘッジ手段を提案・実行している。先物予約、オプション取引、通貨スワップなど、顧客のニーズに応じた最適なヘッジ戦略を提供している。
貨物海上保険の手配 では、輸送中の貨物損害リスクをカバーする保険を手配している。商社の持つ保険会社とのネットワークを活用して、適切な保険条件での手配を実現している。
グループ金融機能の活用
総合商社各社は、グループ内金融機能の強化により、資金効率の向上と金融コストの削減を図っている。グループファイナンス会社の設立により、グループ内資金の集中管理を実現している。
キャッシュマネジメントシステムでは、グループ各社の資金過不足を効率的に調整している。資金余剰のある会社から資金不足の会社への資金移動を自動化することで、グループ全体の資金効率を向上させている。
ネッティングシステムでは、グループ内取引の相殺決済により、決済件数と決済金額の削減を実現している。これにより、事務コストの削減と決済リスクの軽減を図っている。
外貨集中管理では、グループ各社の外貨建て債権・債務をグループファイナンス会社に集約し、為替リスクの一元管理とヘッジコストの削減を実現している。
7.主要事業分野と戦略
資源・エネルギー分野
資源・エネルギー分野は、総合商社の収益基盤として最も重要な事業領域である。石油・天然ガス、鉄鉱石・石炭、非鉄金属、ウラン・再生可能エネルギーなど、多様な資源・エネルギー源への投資と取引を行っている。
石油・天然ガス事業では、上流の開発・生産から、中流の輸送・貯蔵、下流の精製・販売まで、バリューチェーン全体にわたって事業を展開している。特に液化天然ガス(LNG)事業では、長期契約による安定供給と投資収益の確保を両立させている。
鉄鉱石・石炭事業では、主要な資源産出国であるオーストラリア、ブラジル、インドネシアなどで大型鉱山を操業している。中国をはじめとするアジア諸国の鉄鋼需要を背景として、安定的な収益基盤となっている。
非鉄金属事業では、銅、亜鉛、ニッケル、アルミニウムなどの鉱山開発と製錬事業に参画している。電気自動車や再生可能エネルギーの普及に伴う需要拡大を見込んで、戦略的な投資を継続している。
再生可能エネルギー分野では、太陽光、風力、地熱、バイオマスなど多様な発電事業に取り組んでいる。脱炭素社会への移行を見据えて、従来の化石燃料中心から再生可能エネルギーへのポートフォリオ転換を進めている。
機械・インフラ分野
機械・インフラ分野では、プラント輸出から始まって、インフラ投資・運営へと事業領域を拡大している。電力、交通、水処理、通信などの社会基盤整備において、単なる設備供給者から事業運営者への転換を図っている。
電力事業では、発電所の建設・運営から電力小売まで、電力バリューチェーン全体に参画している。特に新興国での電力インフラ整備需要を背景として、長期的な安定収益の確保を目指している。
交通インフラでは、鉄道、道路、港湾、空港などの整備・運営事業に参画している。都市化の進展に伴うインフラ需要の拡大を背景として、PPP(官民連携)方式での事業参画が増加している。
水処理事業では、上水道、下水道の整備・運営に加えて、産業用水処理、海水淡水化などの事業に取り組んでいる。水資源の希少化と水質規制の強化を背景として、成長分野として位置づけられている。
通信・IT分野では、海底ケーブル、データセンター、5G基地局などの情報通信インフラへの投資を拡大している。デジタル化の進展に伴うインフラ需要の拡大を取り込む戦略である。
化学・素材分野
化学・素材分野では、基礎化学品から高機能材料まで、幅広い化学製品の取引と投資を行っている。特にアジア市場での需要拡大を背景として、現地での製造・販売事業への参画を拡大している。
基礎化学品では、エチレン、プロピレンなどの石油化学基礎原料から、各種化学製品の製造・販売に取り組んでいる。中国、インド、東南アジアでの石油化学コンプレックスへの投資を通じて、アジア市場での地位確立を図っている。
高機能材料では、電子材料、自動車材料、航空機材料など、高付加価値製品の取引を拡大している。日本企業の技術力を活かして、グローバル市場での販売網構築に取り組んでいる。
肥料事業では、リン酸、カリ、窒素肥料の製造・販売を行っている。世界人口の増加と食料需要の拡大を背景として、安定的な成長が期待される分野である。
樹脂・合成繊維分野では、ポリエチレン、ポリプロピレン、PETなどの汎用樹脂から、エンジニアリングプラスチックまで幅広く取り扱っている。包装材料、自動車部品、電子部品など多様な用途での需要拡大に対応している。
生活消費財分野
生活消費財分野は、総合商社の事業ポートフォリオの中で近年急速に拡大している分野である。食料、繊維、生活用品、小売・流通など、消費者に身近な商品・サービスを幅広く手がけている。
食料事業では、穀物、食肉、水産物、加工食品など、食料サプライチェーン全体にわたって事業を展開している。世界人口の増加と新興国での食生活向上を背景として、長期的な成長が期待される分野である。
小売・流通事業では、コンビニエンスストア、スーパー、百貨店、専門店など多様な業態への投資を行っている。特にアジア新興国での中間所得層拡大を背景として、現地小売事業への参画を拡大している。
ブランド・ライセンス事業では、有名ブランドの日本・アジア地域でのライセンス事業を展開している。ファッション、化粧品、食品など多様な分野でブランド価値を活用した事業を推進している。
物流・サプライチェーン事業では、3PL(サードパーティロジスティクス)、倉庫運営、配送サービスなど、効率的な物流システムの構築・運営に取り組んでいる。Eコマースの拡大に伴う物流需要の増加に対応している。
金融・保険分野
金融・保険分野では、総合商社の持つ顧客基盤と信用力を活かして、多様な金融サービスを提供している。単なる自社の資金調達・リスク管理を超えて、外部顧客向けの金融事業としても展開している。
リース・レンタル事業では、自動車、建設機械、医療機器、航空機など多様な設備のリース・レンタルサービスを提供している。特に新興国での設備需要拡大を背景として、海外でのリース事業を拡大している。
保険事業では、損害保険、生命保険の取扱いに加えて、保険会社への出資・経営参画も行っている。特にアジア新興国での保険需要の拡大を見込んで、現地保険会社との合弁事業を推進している。
銀行業では、商業銀行、投資銀行業務への参画を通じて、金融サービスの提供範囲を拡大している。特に貿易金融、プロジェクトファイナンス分野での専門性を活かした事業展開を行っている。
フィンテック分野では、決済サービス、電子マネー、クレジットカード、オンライン融資など、新しい金融サービスへの投資を拡大している。デジタル化の進展に対応した金融サービスの革新に取り組んでいる。
8.グローバル展開と地域戦略
海外展開の歴史と現状
総合商社の海外展開は、明治期の貿易仲介業務から始まり、現在では世界約90カ国・地域に約1,000拠点を展開する規模まで拡大している。各拠点は単なる駐在員事務所を超えて、現地での事業運営拠点として機能している。
戦後復興期には、原料輸入と製品輸出のための海外ネットワーク構築が主目的であった。しかし、1980年代以降の投資機能強化に伴い、海外拠点は投資案件の発掘・実行・管理を担う戦略拠点へと性格を変化させた。
現在の海外拠点は、地域統括会社、事業会社、駐在員事務所に大別される。地域統括会社は特定地域での事業戦略の立案・実行を担い、事業会社は現地での具体的な事業運営を行っている。
海外展開においては、現地の文化・商慣習への理解と適応が重要である。各社とも現地採用の人材育成に力を入れ、日本人駐在員と現地スタッフの協働による効果的な事業運営を実現している。
アジア戦略
アジア地域は総合商社にとって最も重要な海外市場である。中国、ASEAN、インドを中心として、人口増加と経済成長を背景とした多様な事業機会が存在している。
中国市場では、世界第2位の経済規模を背景として、資源・エネルギーの供給、製造業への投資、消費者向けサービスなど幅広い分野で事業を展開している。特に環境・省エネ分野での日本企業の技術力を活かした事業展開に注力している。
ASEAN市場では、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピンなどで自動車、化学、消費財分野への投資を拡大している。ASEAN経済統合の進展により、域内での効率的な事業展開が可能となっている。
インド市場では、IT・デジタル分野での急速な発展と巨大な消費市場を背景として、製造業、小売業、金融業への投資を強化している。複雑な規制環境への対応が課題となっているが、長期的な成長ポテンシャルは極めて高い。
アジア域内での三国間取引も重要な事業である。原料をある国から調達し、別の国で加工して、第三国で販売するという域内完結型のビジネスモデルの構築に取り組んでいる。
北米・南米戦略
北米市場では、世界最大の経済規模と成熟した市場環境を背景として、高度な事業展開を行っている。特に資源開発、インフラ投資、金融サービス分野での事業が中心となっている。
米国では、シェールガス・シェールオイル開発への投資、再生可能エネルギー事業、物流・インフラ事業への参画を拡大している。規制環境の透明性と法制度の安定性を活かして、長期的な投資を推進している。
カナダでは、豊富な天然資源を背景として、石油・天然ガス、鉱物資源の開発に参画している。環境規制の強化に対応して、環境負荷の少ない開発手法の採用に取り組んでいる。
南米市場では、ブラジル、チリ、ペルーなどで資源開発と農業投資を中心とした事業を展開している。政治・経済の不安定性がリスク要因となっているが、豊富な天然資源と農業ポテンシャルは魅力的である。
ブラジルでは、大豆・トウモロコシなどの穀物生産、鉄鉱石・ニッケル採掘、製紙・パルプ生産などの事業に参画している。現地企業との合弁により、政治リスクの軽減を図っている。
欧州・中東・アフリカ戦略
欧州市場では、先進的な環境技術と厳格な環境規制を背景として、クリーンエネルギー、環境技術分野での事業展開を重視している。
英国では、北海油田開発、洋上風力発電、金融サービス業への投資を行っている。Brexit後の規制環境変化への対応が課題となっているが、引き続き重要な市場として位置づけている。
ドイツでは、自動車産業、化学産業への投資に加えて、再生可能エネルギー、環境技術分野での協業を拡大している。技術力の高いドイツ企業との連携により、新技術の獲得・活用を図っている。
中東地域では、豊富な石油・天然ガス資源と資金力を背景として、エネルギー・化学分野での事業を中心としている。特にUAE、サウジアラビア、カタールなどのGCC諸国での事業展開を重視している。
アフリカ地域では、豊富な天然資源と高い経済成長ポテンシャルを背景として、資源開発とインフラ整備への投資を拡大している。政治・経済の不安定性と インフラの未整備がリスク要因となっているが、長期的な成長期待は高い。
新興国戦略の課題と機会
新興国での事業展開においては、高い成長ポテンシャルと様々なリスクが混在している。政治リスク、為替リスク、規制リスクなどへの適切な対応が事業成功の鍵となっている。
現地パートナーとの協働は新興国戦略の重要な要素である。現地の商慣習、規制環境、政治情勢に精通したパートナーとの連携により、リスク軽減と事業機会の拡大を同時に実現している。
人材育成も重要な課題である。現地での事業運営を担う人材の育成と、日本との橋渡し役となる人材の確保が、持続的な事業成長のために不可欠である。
ESG(環境・社会・ガバナンス)への配慮も新興国事業において重要性を増している。環境負荷の軽減、地域社会への貢献、透明性の高い企業統治を通じて、持続可能な事業展開を実現している。
9.持続可能経営とESG
ESG経営の重要性
総合商社にとってESGへの取り組みは、単なる社会的責任を超えて、事業継続性と競争力確保のための戦略的課題となっている。グローバルに事業を展開し、長期投資を行う商社にとって、持続可能性の確保は不可欠である。
環境分野では、気候変動対応が最重要課題となっている。パリ協定に基づく脱炭素社会の実現に向けて、商社の事業ポートフォリオの転換が求められている。従来の化石燃料中心から再生可能エネルギーへのシフト、環境負荷の少ない事業モデルの構築が急務となっている。
社会分野では、人権尊重、労働環境改善、地域社会への貢献が重要な課題である。グローバルに事業を展開する中で、各地域の社会課題解決に貢献する事業の推進が求められている。
ガバナンス分野では、透明性の高い企業統治、リスク管理体制の強化、ステークホルダーとの対話促進が重要である。多様な事業を営む商社にとって、適切なガバナンス体制の構築は事業リスクの軽減に直結している。
脱炭素戦略の推進
脱炭素社会の実現に向けて、総合商社各社は包括的な戦略を策定している。2050年カーボンニュートラル目標の設定、再生可能エネルギー事業の拡大、炭素集約度の高い事業からの撤退などの取り組みを進めている。
再生可能エネルギー事業では、太陽光、風力、地熱、バイオマス、水力など多様な発電事業への投資を拡大している。特に洋上風力発電は大型化が可能で、安定的な収益が期待できるため、戦略的な投資対象となっている。
水素・アンモニア事業は、脱炭素社会における重要なエネルギー源として注目されている。グリーン水素の製造、輸送、利用に関する一貫したバリューチェーンの構築に取り組んでいる。
炭素回収・利用・貯留(CCUS)技術への投資も進めている。二酸化炭素の回収・貯留により、化石燃料使用時の環境負荷軽減を図る技術で、脱炭素移行期の重要な技術として位置づけられている。
石炭火力発電事業からの撤退も進めている。環境負荷の高い石炭火力発電への新規投資を停止し、既存事業についても段階的な撤退を検討している。
サーキュラーエコノミーへの対応
循環型経済(サーキュラーエコノミー)の実現に向けて、総合商社は資源循環ビジネスの構築に取り組んでいる。従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済モデルから、資源を循環利用する持続可能なモデルへの転換が求められている。
リサイクル事業では、金属、プラスチック、紙などの廃棄物を回収・再生する事業に投資している。特に希少金属のリサイクルは、資源確保と環境負荷軽減の両立を図る重要な事業である。
バイオマス事業では、農業廃棄物、林業残材、食品廃棄物などを原料として、バイオ燃料、バイオ化学品、バイオプラスチックなどを製造する事業に取り組んでいる。
廃棄物発電事業では、都市ゴミや産業廃棄物を燃料として発電を行う事業に参画している。廃棄物の適正処理と再生可能エネルギーの創出を同時に実現する事業モデルである。
デジタル技術を活用した効率化も重要である。IoT、AI、ビッグデータ分析により、資源利用効率の向上、廃棄物削減、エネルギー使用量最適化などを実現している。
10.まとめーー総合商社とは何か?
総合商社は日本独特のビジネスモデルです。単純な貿易仲介業ではなく、「トレーディング」「事業投資」「事業経営」という3つの機能を組み合わせて運営しています。商品を売り買いするだけでなく、自ら投資して事業を育て、経営にも参画する総合的な企業です。
歴史的な発展
明治時代の貿易商から始まり、財閥系の商社へと発展しました。戦後の外貨不足の時代には、食料やエネルギーの確保で国家的な役割を果たしました。高度経済成長期には物流や金融、大型プロジェクトの機能を充実させ、1980年代からは資源開発への投資、2000年代以降はインフラやデジタル分野にも進出しています。
収益構造の特徴
取扱高は巨額ですが、実際の利益は営業収益に集約されます。最近では配当や持分法による投資収益への依存が高まっています。ただし、資源価格の変動に業績が左右されやすいという課題があります。そのため各社は事業の多角化を進め、リスク管理を高度化しています。国別リスク、市況変動リスク、為替リスクなどを総合的に管理し、J-SOX法に準拠したガバナンス体制と多段階の投資審査プロセスを整備しています。
資金調達と金融機能
高い信用格付けを背景に、社債発行やコマーシャルペーパー、銀行からの協調融資を組み合わせて資金調達しています。グループ全体の金融機能を活用して、為替や流動性を最適化しています。貿易取引では信用状の発行、為替ヘッジ、海上保険などの金融サービスを提供し、顧客のビジネスを資金面からもサポートしています。
主要な事業分野
現在の事業は大きく5つの柱に分かれています。
- 資源・エネルギー事業
- 機械・インフラ事業
- 化学・素材事業
- 生活消費財事業
- 金融・保険事業
各分野で国内外の需要変化に対応した戦略的投資を続けています。アジア新興国ではサプライチェーンの統合と三国間取引、インフラ運営が中心です。北米や中東では資源権益の確保と再生可能エネルギー開発が主力となっています。
ESG経営への転換
近年はESG(環境・社会・ガバナンス)経営が競争力の決め手となっています。2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、再生可能エネルギーの拡大、水素・アンモニア事業、CO2回収・利用・貯留技術(CCUS)、循環型経済事業を加速させています。
これに伴い、石炭火力発電からの撤退と環境負荷の少ないポートフォリオへの転換が進んでいます。
今後の展望
総合商社は「幅広い事業展開」と「投資家としての機能」を両立することで、環境や技術、社会のニーズ変化に素早く対応しながら、長期的な企業価値を創出するビジネスモデルへと進化しています。このビジネスモデルこそ、総合商社の究極の魅力であり、他業界との差別化ポイントだと考えています。
最後に、ここまで長きにわたる解説を読んでいただきありがとうございます。「何かここ間違っていないか?」「ここは何をいっているのだろう?」と思った方は、是非ともOB/OG訪問を活用してください。
前編をまだ見ていない方
商社に関するその他コラムはこちら
結局商社ってなにやってるの? 商社ビジネスを簡単解説!
【文系】27卒の就活はいつから始まる?25卒・26卒の先輩から学ぶ勝ち組の就活スケジュールとは
5大総合商社(三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、丸紅)の特徴を徹底比較!【強み・社風】
【業界研究】 総合商社編
「右から左に流すだけ」ではない。総合商社のトレーディング業務を簡単解説!
27卒の総合商社・専門商社募集情報まとめ【早期・本選考・選考直結・インターン】
「外資就活ドットコム」で早期就活の情報をチェック
「外資就活ドットコム」は外資・日系双方の選考対策に役立つ就職活動サイトです。無料で会員登録できますのでぜひご活用ください。
- 外資・日系企業の企業ページで企業研究を進め、毎日更新される募集情報をチェックできる(限定募集情報や特別なイベントも多数あります)
- インターンや本選考ごとに、先輩就活生のES・選考体験記を読み、最新の情報で具体的な選考対策ができる
- 就活に役立つ選考情報コラムのほか、5年先・10年先のキャリアプランニングに役立つ記事など、あらゆる局面で役立つコラムを多数掲載
...
会員登録して全ての内容を見る
続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。
外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。
この記事を友達に教える



