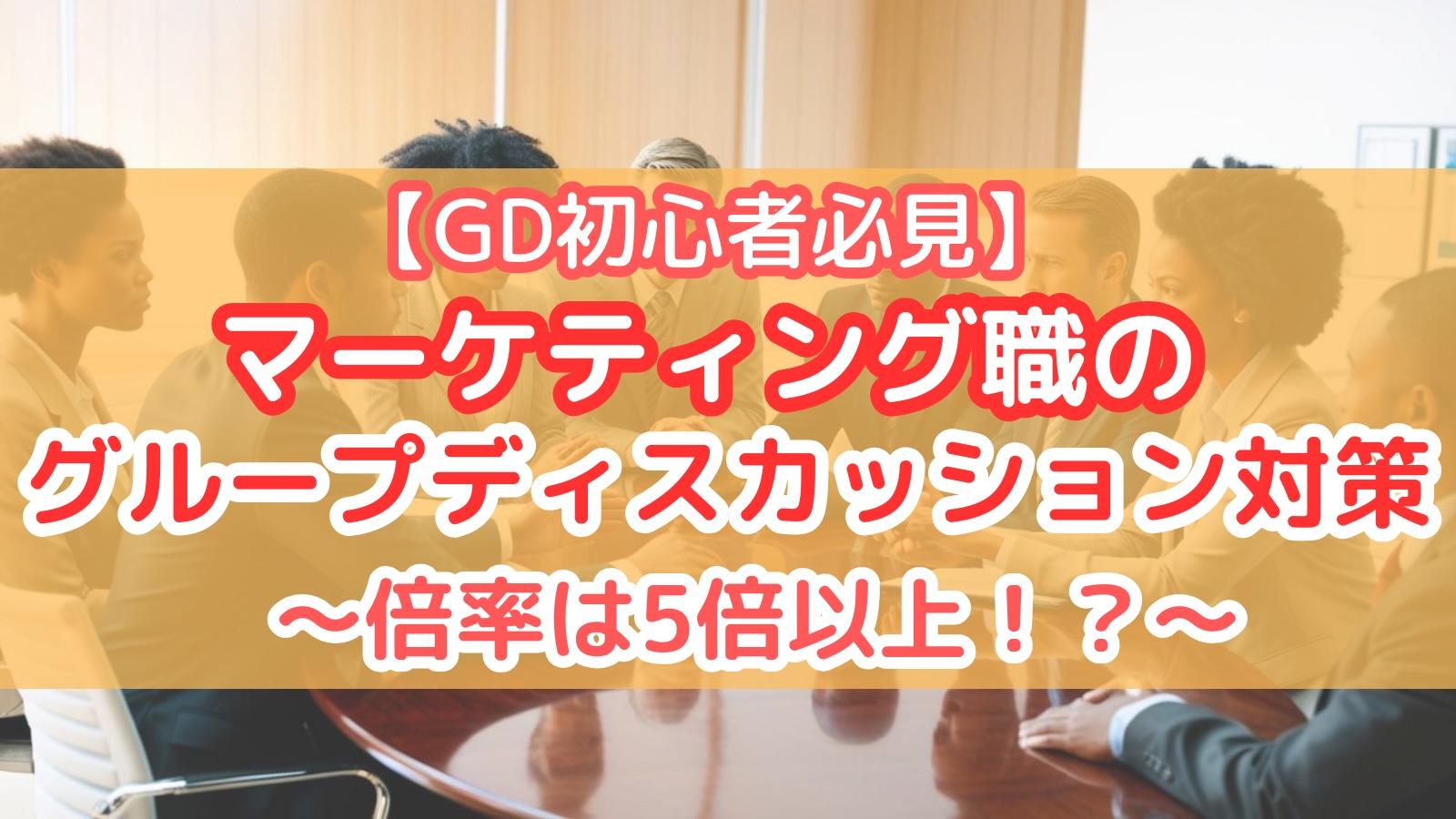
【GD初心者必見】マーケティング職のGD(グループディスカッション)対策~倍率は5倍以上!?~
2025/08/05
会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
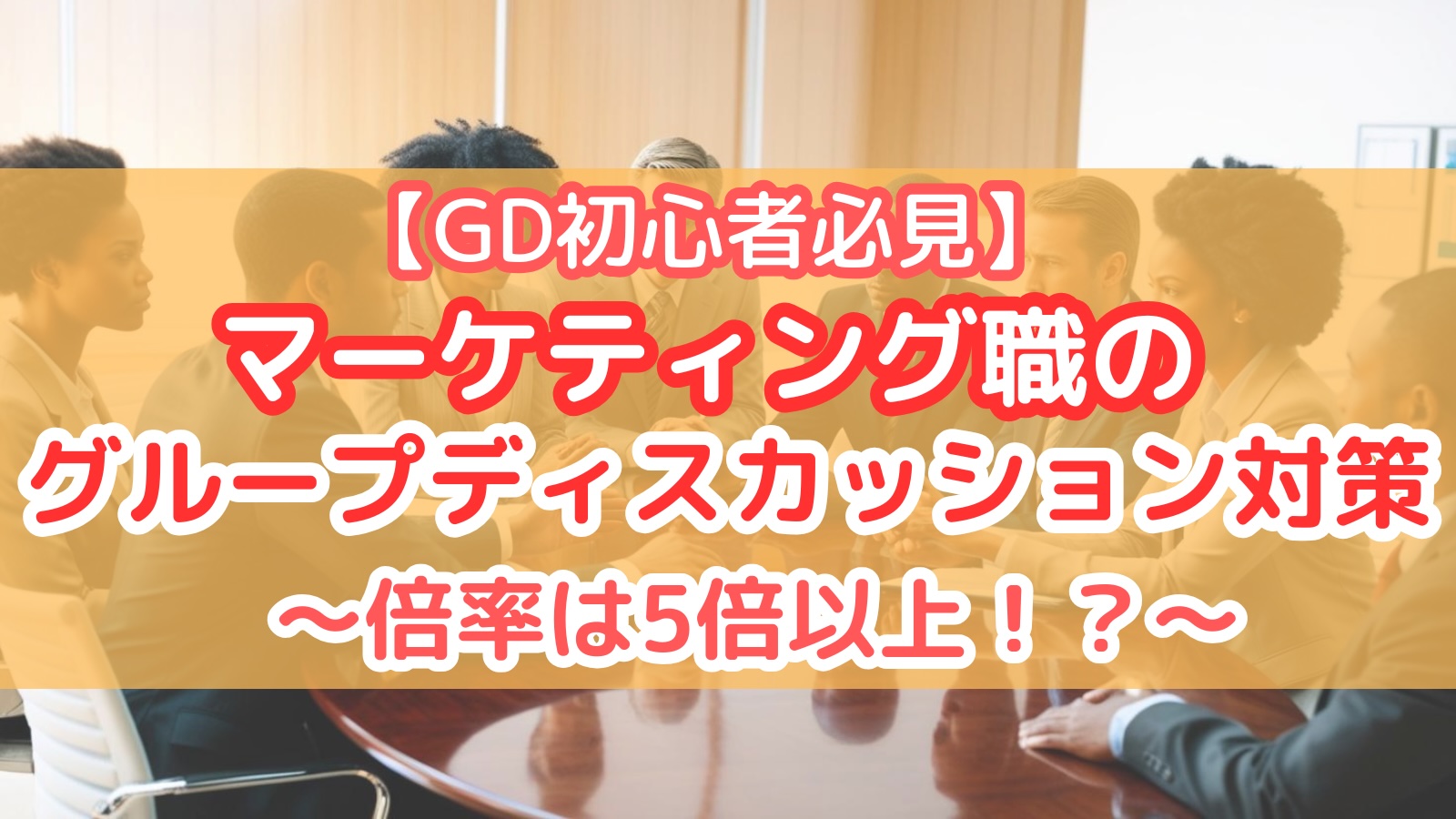
こんにちは、外資就活 コラムチームです。
マーケティング職を採用している外資系企業のGD選考は、なんと 倍率が5倍以上 あるといわれています。職種別採用を行っている外資系企業の選考の中でも、「GD選考」は大きな壁の一つであると言えるでしょう。
本コラムでは「GDって何?」という方でも十分に理解していただける形で、GDの概要から対策方法までご紹介します。 GD対策はマーケティングのジョブ対策の基礎にもなる ので、マーケティング職を志望している方は必読です!また本コラムで紹介するエッセンスは、総合商社・難関事業会社・ベンチャーなどでも使用できますので、 他業界志望の方もぜひご一読ください!
筆者は就活生時代、多くのGD選考を経験し、最終的にGD選考の通過率は9割を超えることができました。そんな私の経験や、どのようにGDの選考対策を行っていたかなどもお伝えしたいと思います。なお、このコラムがGD選考対策の全てではありません。あくまでもGD選考に対する1人の意見として捉えていただければ幸いです。
マーケティング職の概要やマーケティング職を採用している企業の特徴、選考スケジュール、マーケティング職以外の職種(ファイナンス職やセールス職)などに関しては、以下のコラムを参照してください。
・外資系マーケティング職の仕事内容と求められるスキル|マーケティング=市場調査ではない?
・【マーケティング職志望必見!企業研究】P&G、ユニリーバ、USJ、ロレアルの違いとは。
・外資マーケターを求める企業の選考内容・スケジュールまとめ
・外資系企業の「ファイナンス職」「セールス職」とは?各職種の業務内容、必要な能力、キャリアパスを解説
GDとはどのような選考なのか
GD(グループディスカッション)とは?
企業の選考方法において、グループワークは業界問わず頻繁に登場します。代表的なものとして、3~10人で一定時間内に課題に対する解決方法を考えるGD(グループディスカッション)があります。
...
会員登録して全ての内容を見る
続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。
外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。
この記事を友達に教える


