会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
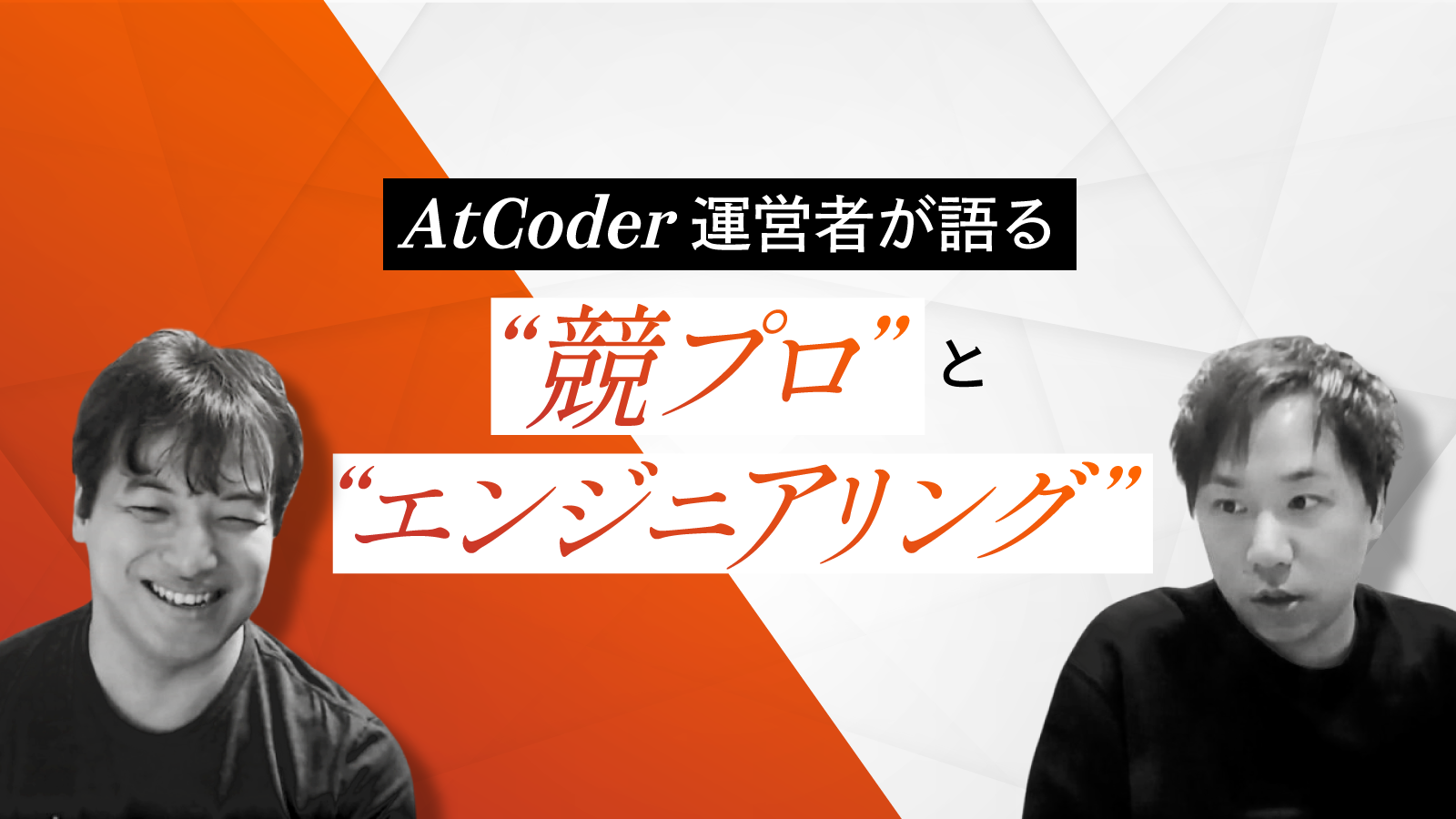
ソフトウェアエンジニア志望で、AtCoderを知らない学生はいないだろう。エンジニア就活において、それほどこの競技プログラミング(競プロ)サービスは知られている。その理由の一つは、プログラミングスキルの鍛錬としてこのサービスが活用されているからだ。
日本発のこのプラットフォームは、学生、社会人を問わず多くの学生に利用されていている。そして、スキルレベルの指標となるレーティングを示す「色」は、競プロ参加者だけではなく、企業側からの評価対象にもなっているという。その、実状とは——。
AtCoder代表の高橋直大さんと副社長の青木謙尚さんへのインタビューを通し、競プロと就活、ソフトウェアエンジニアリングのつながりを探った。【北川直樹】
写真左/高橋直大(たかはし・なおひろ)
AtCoder株式会社 代表取締役社長。
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。2012年にAtCoderを創業。2008年にマイクロソフト主催の「Imagine Cup 2008」Algorithm部門で3位入賞したのを皮切りに、世界的なプログラミングコンテストで高成績を出し続けている。
同右/青木謙尚(あおき・けんしょう)
AtCoder株式会社 取締役副社長。
和歌山大学大学院システム工学研究科中退。2012年にAtCoderを創業。以後、会社経営に関わる全てのことを行う。バックグラウンドにあるソフトウェアエンジニアとしての知見を活かした職業紹介なども行なっている。
◆内容や肩書は2025年4月の記事公開当時のものです。
企業が見る「AtCoderのレート」とは?
——AtCoderのレートについて、エンジニア採用をしている企業がどのように評価しているのか聞くことはありますか。
青木:あります。企業の採用担当者からは一般的に、緑以上のレート(*)を持ってる学生が優秀と評価されることが多いです。このレベルに至るには、コンテストに一定出続ける必要があるので、その姿勢も含めて評価されるというのが実態ですね。
高橋:緑に到達するには、継続的な取り組みが必要です。毎週土曜にあるコンテンストに出て、3〜4ヶ月くらいを費やしてやっと到達するくらいの難易度のため、地道にことに向き合えるスタンスそのものが高く評価される部分が大きいのだと思います。
*:緑はAtCoder参加者の上位30%。AtCoderのランクについては、公式ページで詳細を確認できる
——そもそも「緑」はどれくらいの割合の人が到達できるのでしょう。
青木:10回以上コンテストに参加したユーザーで見ると、緑以上のレートに到達しているのは約4割くらいです。つまり、一定期間継続して参加しても、半分以上の人は緑に届かないという現実があります。
高橋:緑に到達するには論理的な思考力、自分の考えをプログラムで表現できる力を持っているかが問われます。そのため、緑になっている時点で「一定以上できる人」と言ってよいと思います。
——実際に企業の採用担当者から、レートに関する問い合わせはあるんでしょうか。
青木:はい、あります。一番多いのは「緑以上のレートの人ってどれくらいいるんですか?」という質問ですね。AtCoder側でも統計を出していて、企業から注目されている指標になっていると感じます。
——レートが高い学生に対し、企業側が抱く印象などを聞くことはありますか。
高橋:毎週継続的にコンテストに参加しているという点がまず評価されます。「コードを書くのが好きなんだな」と伝わりますし、それを楽しんでやっているという姿勢もプラスです。レートが高いということで、「やり切る力」が高く評価されるのは間違いないですね。
——企業によって評価のされ方には違いはあるんでしょうか。
青木:あります。例えばアルゴリズムを重視する企業では、AtCoderのレートを重視する傾向があります。一方で、チーム開発や可読性を重視する企業では、レートだけでなく開発経験やチームでの振る舞いも見られます。
高橋:企業によって求める人物像は違うので、レートだけを見て採用するということはないと思います。ただ、レートが高いことは強いアピール材料になるのは間違いありません。
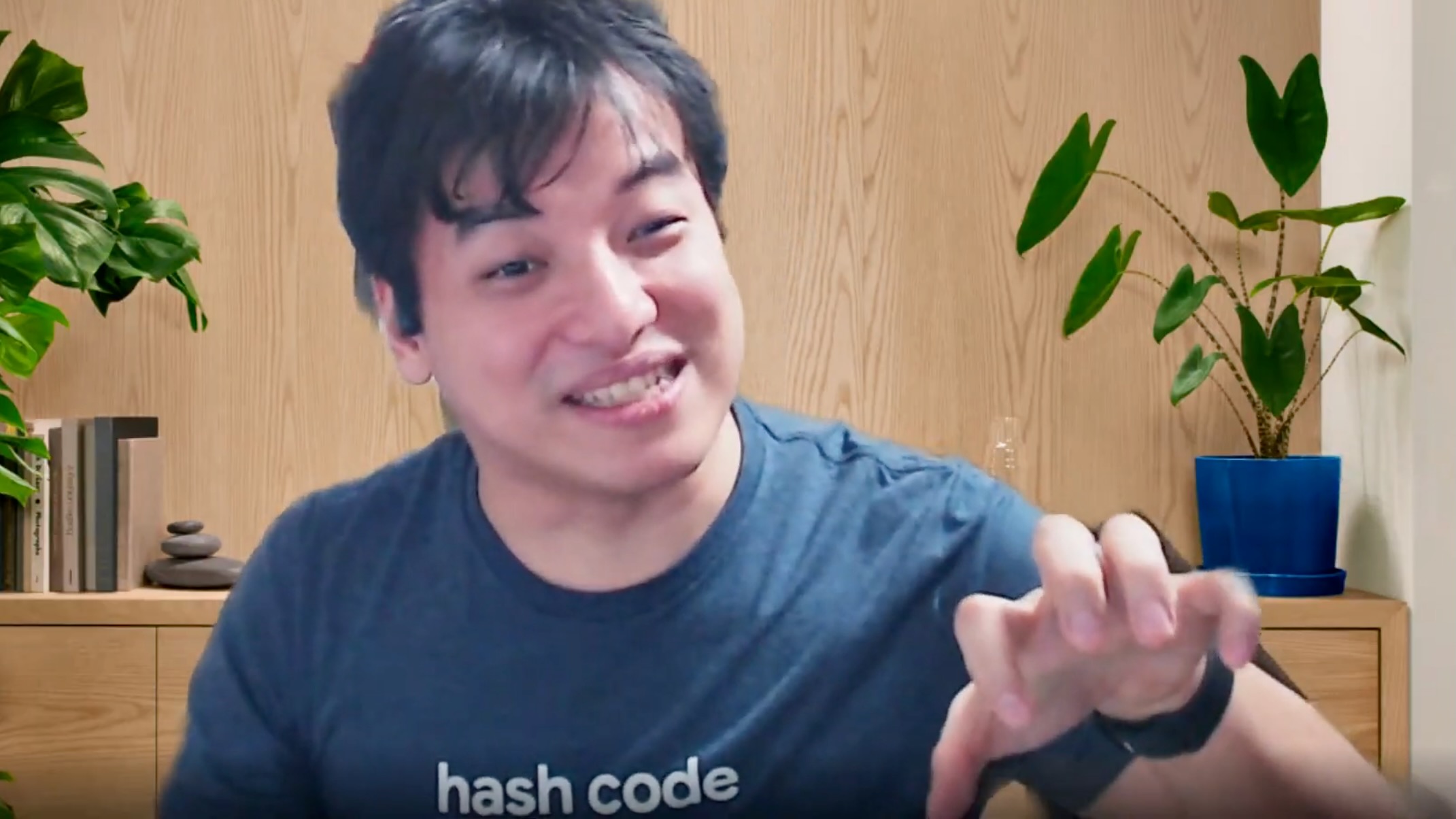
◆インタビューはオンラインで実施
競プロスキルと実務スキルの違い、共通点
——AtCoderで鍛えた力と、エンジニアの実務スキルはどのように重なるんでしょうか。
高橋:競プロでも仕事でも、やるべきことを把握して、それを実現するためのアイデアを考え、実装するというステップがあります。この一連の流れはAtCoderと共通しています。特に、情報を整理し、ロジックを考えて、それをコードに落とし込んでいくという流れは重なっていますね。
青木:AtCoderの参加者は自分がまだ使ったことのない技術をキャッチアップする速度が速いです。新しい業務領域にも早く適応できる人が多いように感じますね。レートが高い人ほど、環境に適した学習や振る舞いができるなという印象です。
——AtCoder上で評価される能力で活かしやすいスキルは具体的にどんなものでしょう。
高橋:問題を正確に理解し、複雑な内容を自分の中で簡潔に整理して、それを実装する力です。特に「アイデアをコードに落とし込むスピードと正確性」は、どんな職種でも活きてくる力だと思います。
青木:AtCoderで用いるスキルとして、例えば複雑なグラフ構造を整理して処理する能力や、最短経路のような問題を効率よく解く能力は、思考力のトレーニングとしても非常に有用です。それがエンジニアの業務に応用されるケースも少なくありません。
——反対に、エンジニアの実務ではどんなスキルがAtCoderとは異なりますか。
青木:ネットワークやミドルウェアの設定、チーム開発に必要なコードの可読性や設計力など、実務特有のスキルはAtCoderでは身につかないです。特にチーム開発の中での振る舞いや、可読性を意識した設計などはまた別の学習が必要ですね。
高橋:AtCoderは1人で完結する競技です。チームで動くプロジェクトにおけるコミュニケーションや、周囲と協調して進める力は、別途育てる必要があると思います。
——そういったギャップを埋めるにはどうすれば良いのでしょうか。
青木:基本情報や応用情報技術者試験などで問われるような、インフラやネットワークの常識を学ぶのも有効だと思います。こういったものは情報系の学部であればカリキュラムに含まれていることも多いですが、独学でもカバー可能だと思います。
高橋:AtCoderで得られる「メタ認知力」や「学習速度の速さ」があれば、業務に必要な知識もスムーズに吸収できるはずです。重要なのは、そこに向き合う意志があるかどうかですね。
——チーム開発に必要な能力と、AtCoder経験の関連性はありますか。
青木:直接的には関連しづらいですが、論理的思考力や課題解決力という意味では土台になる部分は多いです。ただ、チームでの合意形成やドキュメント整備、可読性の高いコードを書くといったスキルは、実際の開発経験を通じて身につける必要があると思います。
高橋:AtCoderだけで完結させようとするのではなく、実務的なプロジェクトにも参加して、幅広くスキルを育てていくことが大事です。

AtCoderをキャリアにどう活かすか
——競プロで得たスキル、力をキャリアに活かすには、どんな選択肢があるんでしょうか。
青木:エンジニアの道をイメージしやすいかもしれませんが、最近はコンサルや金融、クオンツなど直接的にコードを書かない職種で就職する学生も増えています。
これは論理的に物事を把握し複雑な状況を整理して解決する力が、そういった職種でも求められているからだと思います。
——エンジニアのキャリアを選ぶ場合、注意すべき点はありますか。
青木:エンジニアのキャリアを考えた時、技術力だけで勝負しようとするのはとてもハードだということは知っておく必要があると思います。
技術一本で勝負するには、それだけ突き抜けた能力と成果が必要です。自分がそこに対し、本当に覚悟を持って取り組めるかどうかを見極める必要があると思います。
当社で言うと高橋は技術で突き抜けているので、そこで戦っていく自信も覚悟も持っているのですが、私は正直技術一本だけでやっていくほどの自信は持っていません。でも、ビジネスパーソンとして考える時、そのほかの能力やスキルとあわせて戦えるわけですから、視野を広く持って自分に適した働き方を考えていけば良いんです。この思考は持っておいた方がいいでしょう。
高橋:いま青木が言った観点は踏まえた上で、エンジニアは自身の技術力に加えてチームでの振る舞いや、ビジネス的な観点を持ち合わせていると市場価値は高くなります。設計や運用の視点も持てるようになると、長期的なキャリアの幅は広がると思います。
AtCoderでは、このような視点でもエンジニアのキャリア支援をできるように取り組んでいこうと考えています。そのために、競プロにとどまらないサービスを提供していきたいと思いますし、エンジニアの学びの場を作っていければと考えています。
おわりに
競技プログラミングで培った力は、単なるアルゴリズム能力にとどまらず、抽象化力、実装力、学習スピードといった形で多くの企業に求められている。ただし、それをエンジニアリングで活かせる力に変えるには、実務に対する理解と学習姿勢が不可欠だ。
競プロで高いレートを持つ人にこそ、自身の可能性を広げるキャリア戦略を描いてみてほしい。
会員登録すると
このコラムを保存して
いつでも見返せます
マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事
P&G アクセンチュア
内定攻略 会員限定公開
トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム
この記事を友達に教える




