会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
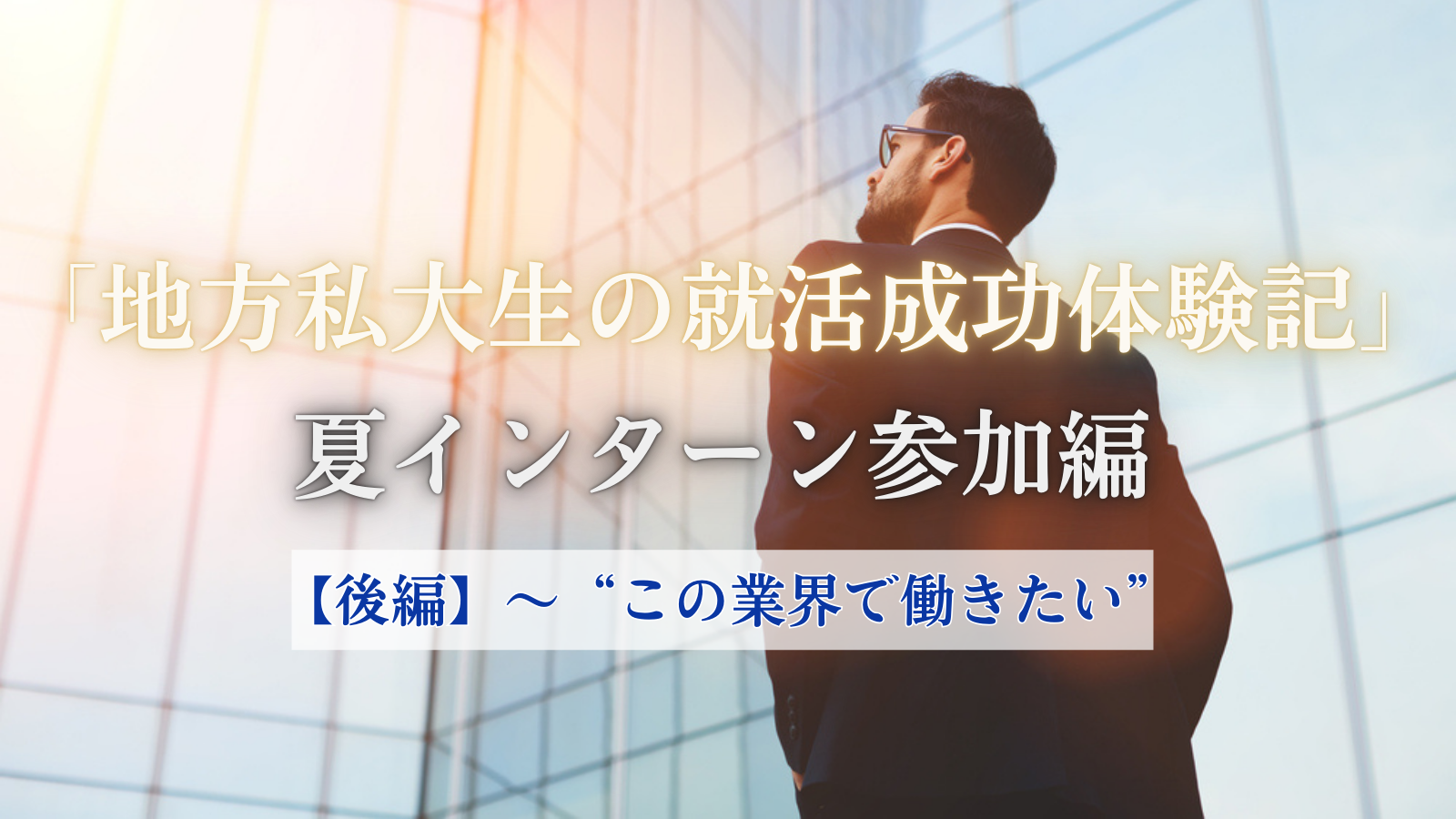
こんにちは!メーカー業界で内定を獲得した、地方私立大学に通う者です。今回は、難関大ではない、資格やサークル、アルバイトでの強みがそんなにない学生の皆さんに、インターン参加を通じて就活を成功させるためには何をすればいいかについて、これから就活が本格化する方たちにお伝えできればと思います。
前回の記事では、夏インターン参加体験記の前編として、私のインターンの選び方や、参加してわかったインターンの種類について書きました。今回は、インターン参加のメリットや、優遇について書いていきます。前編をまだご覧になっていない方は、あわせてご覧ください。
インターンは企業を知るためだけの場じゃない
実際に参加してみて強く思ったのは、“企業理解”を超えた学びや変化が山ほどあるということでした。
ここでは、インターンで得た経験の中で、就活の本選考に直結する気づきや準備の進化について詳しくまとめていきます。
社員との対話が「働く自分」を想像させてくれた
多くのインターンでは、ワークだけでなく社員との座談会や懇親会の時間が設けられています。
この時間が予想以上に貴重で、私は“働く”ということが一気に身近に感じられるようになりました。
特に印象的だったのは以下のような視点です。
- 若手社員の話から、配属後すぐに任される仕事のリアルが見えた
- 出世スピードや異動の実情など、HPでは分からない“現実”が聞けた
こうした会話から、単に「興味がある」ではなく、「この会社でこう働いている自分がイメージできる」という実感を持てるようになりました。
座談会の情報は“その場で終わらせない”のがカギ
座談会で聞いた話は、本選考での志望動機や逆質問のネタとしてめちゃくちゃ役立ちます。
でも、何となく聞いているだけでは記憶に残らず、あとで使いづらくなる。そこで私は次のような工夫をしていました。
【社員の話は“5W1H”でメモをとる】
- 名前や立場も書いておくと、後で志望動機に“実名ベース”で反映しやすい
【話を聞いた後、すぐ自分の感想を書き出す】
- 「この仕事は大変そうだけど、やりがいがあるかも」
→ こうしておくと“ただ聞いた”から“自分の判断軸が明確になった”に昇華できる
【志望動機や逆質問の種に育てる】
- 逆質問では「現場の方から◯◯というお話を聞いたのですが、それは全体的にも共通しているのでしょうか?」といった“聞きっぱなしじゃない姿勢”が伝わる質問ができるようになる
【社会人との会話で“話し方の距離感”が身についた】
最初の頃は、社員と話すだけでもガチガチに緊張して、声も小さく、何を聞いていいか分からない状態でした。
でも、5社10社と座談会をこなしていくうちに、
- 「質問してもいいですか?」のタイミングや言い方のコツ
- 社員に好印象を持ってもらえる“リアクションやうなずき方”
など、“場慣れによる雰囲気適応力”が少しずつついていきました。
この感覚があったことで、本選考の面接でも「社会人と話すこと」自体への抵抗がなくなっていたと思います。
【グループワークで「無理に目立たない」戦略を身につけた】
インターンでは、チームで議論し、プレゼンをまとめる形式のワークもよく出てきます。
最初の頃は“目立たなきゃいけない”という思いから、積極的に仕切ろうとしたり、自分の意見ばかり話してしまったり。でも、うまくいかないことも多くありました。
そんな中で気づいたのが、
- 議論を整理する・他人の意見を深掘る・全体のバランスを見る役割も重要
- 「あの人がいると進みやすい」と思ってもらえるような動きができると強い
実際、社員からのフィードバックでも「自分の意見だけでなく、周囲との調整が上手かった」と言ってもらえたことで、自分の“強みの出し方”が明確になっていきました。
【企業文化の違いを「空気感」で理解できた】
インターンで複数の企業を回っていると、同じ業界でも会社によって全く雰囲気が違うことに驚かされます。たとえば、
- B社:学生のプレゼンに対してかなり鋭く突っ込む。スピード感重視
- C社:社員同士の雑談も体育会系で上下関係がハッキリしている印象
こうした“空気感の違い”は、実際にその場に行って、社員同士や参加者とのやり取りを目の当たりにして初めて感じられるものでした。
そしてその空気が、「ここで働きたいか?」「自分はこのノリに馴染めるか?」を判断する大事な材料になりました。
【他大学の学生から刺激と焦りをもらった】
特に選考ありのインターンでは、早慶や旧帝の学生と同じグループになることも多く、話す内容やまとめ方、プレゼン資料の作り方などで「うわ、すご…」と思う場面もありました。
でも同時に、
- 「大学名だけでビビる必要はない」
- 「話し方・構成力・協調性なら自分にも強みがある」
と感じられた場面もあり、“他人と比べて落ち込む”から、“自分の強みを見つけにいく”というマインドに変わっていったのも大きな収穫でした。
【自己分析・志望動機に活かせる“実体験”が増えた】
最終的に、夏インターンの経験はESや面接での武器になりました。なぜなら、「企業名を出して、具体的に語れる話題」が圧倒的に増えたからです。
たとえば:
- ガクチカ:「グループワークで進行役を務め、意見の対立を調整した経験」
- 逆質問:「インターン時にお話しいただいた◯◯さんの話に関連して伺いたいのですが…」
こうした“実体験に基づく発言”は説得力があり、面接官の反応も明らかに良くなります。逆に、経験がないと話す内容もどこか借り物感が出てしまい、印象が弱くなりがちです。
【動いた人だけが、秋から“安心して就活できる”】
インターンに参加して得た一番大きな変化は、秋以降に焦らなくなったことかもしれません。
- 志望業界・企業が絞れたので、ESや面接も軸がブレなくなった
- 他の学生より一歩先を見て就活を進められるようになった
周囲が秋からようやく動き始める中、自分はすでに“就活の型”を持っていた。この差が、就活後半での余裕や自信につながったと実感しています。
インターンに出ることは、単なる「企業を知る」以上に、自分を知る、就活を設計する、そして“武器を手に入れる”ことに近い行為だと思います。
夏の数週間をどう過ごすかで、就活全体の景色がガラッと変わる。そんな実感を持てたことが、この経験の一番の成果だったかもしれません。
夏インターン経由の優遇ルートは実在する
夏インターンに参加する最大のメリットのひとつが、「本選考での優遇につながることがある」という点です。就活を始めたばかりの頃は、正直あまり意識していませんでした。
でも、実際に参加してみて分かったのは、「あ、この企業は最初からインターン参加者を早期選考に乗せるつもりだったな」と感じる空気が確かにあるということ。ここでは、先ほどまでの項でたびたび出てきた選考優遇について詳しくご紹介します。
「優遇」ってどんな形で現れるの?
企業によって表現は様々ですが、実際に私が経験したor聞いた優遇ルートの例を挙げると
- Webテスト免除・スコア流用(夏の時点で受けたテストをそのまま利用)
- 一次面接免除 or スキップ
- 早期選考(11月〜2月頃)の特別ルート案内
- “優遇あり”と明言しないが、事実上通過率が異様に高いパターン
私はこの中で、3社でES免除、2社で一次スキップ、1社で完全な早期ルートに乗ることができました。
特に印象的だったのは、夏インターン参加時のグループワークで高評価をもらった企業から、「ぜひ早期の選考に進んでほしい」と声をかけられたケースです。
優遇がある企業の特徴とは?
すべての企業がインターン参加者を特別扱いするわけではありません。私が参加した中で、優遇があるかどうかの“傾向”は以下のようなものでした。
- 金融や保険系は、1dayでも「参加履歴」を記録して本選考で反映している
- 外資・ベンチャー系は、選抜型インターン参加者がそのまま内定直結フローに乗ることもある
逆に、「説明会中心」「コンテンツ重視」のインターンは、本選考との連動が薄いこともありました。
夏の段階で「優遇」を狙いすぎる必要はないが…
正直なところ、就活の序盤で「優遇のある企業だけを狙う」のは難しいですし、全部が全部、評価に直結するわけでもありません。
ただ、意識しておくべきなのは以下の3点です。
【“選ばれて呼ばれている”インターンでは一挙手一投足が評価対象】
選考ありで倍率が高いインターンは、「見るつもりで呼ばれている」という意識を持つと自然と振る舞いにも張りが出る。
【参加後のメールや案内は“企業側の温度感”のバロメーター】
「後日、個別に早期選考をご案内します」「〇月に○○選考の先行予約を開始します」など、その案内の“温度”で自分の評価を推察できる。
【夏のインターンで印象を残せると、その後が圧倒的に楽になる】
早期で面接練習を兼ねたつもりが、そのまま内定に直結したケースも。「早く打席に立てる」ことがどれだけ有利かは、就活が進むほど実感しました。
私が夏のインターンで得た“目に見える成果”
- インターン中の言動を面接官が覚えてくれていた(「プレゼン良かったよね」と言われた)
- 他の就活生がまだ動き始めていないうちに、「1社内定相当の手応え」を持って秋を迎えられた
この「安心感」こそが、夏のうちに動いたことの最大のリターンだったと思います。夏インターンは、就活のすべてを決めるわけではありません。でも、本選考の“入り口”を広げるうえで、これ以上に効率のいい手段はないとも感じました。「優遇があるから参加する」のではなく、「参加したことが結果的にチャンスを呼び込んだ」――それが、私の実感に近いです。
インターンは“内定に近づく練習”であり、“志望度を固めるための旅”でもある
夏インターンに参加した数ヶ月間を振り返ると、本当に濃密で、就活の基礎体力を一気に底上げした期間だったと感じます。面接の場慣れ、社員との会話、ワークでの立ち回り、企業との相性、志望動機の“材料”、そして優遇ルート――。
当初は「とにかく行けるものに行ってみよう」という思いで動き始めた私でしたが、結果的に夏インターンが就活全体の流れを変える転機になりました。
すべての経験が“就活の下地”になる
正直、参加したインターンのすべてが「志望度MAX」の企業だったわけではありません。むしろ、「ここは違うな」と思った会社の方が多かったくらいです。でも、そういった企業にも行ったからこそ、「じゃあ自分に合うのはどこなのか?」を深く考えるようになりました。
そしてその思考が、秋以降のES・面接・企業選びに自然と反映されていった。夏のうちに行動したこと自体が“自己理解”と“戦略設計”につながったのだと思います。
動いた分だけ、秋からの自分に余裕が生まれる
夏の段階である程度“戦える型”を作れていたことは、秋冬の就活において非常に大きなアドバンテージになりました。ESや面接で焦らない、他人の動きに振り回されない、自信を持って企業を選べる。
あの時インターンに出ていなければ、たぶん今ごろ「何を書けばいい?」「どこを受ければいい?」と混乱していたと思います。
これは“選考の前哨戦”であり、“自分探しの旅”でもある
夏インターンを一言でまとめるなら、「内定に近づく練習」でもあり、「志望度と自分軸を固める旅」でもあるということ。
参加することで、評価される場に立ち、自分を伝え、他者と比べ、フィードバックをもらう。その一つひとつの経験が、就活という“本番”に備える上で、何よりの実践になります。
最後に:まだ動いていない人へ
もし今、「夏インターンに乗り遅れたかも」と感じている人がいたら、心配しないでください。私自身も最初は出遅れ組でした。でも、1社動いてみることで、すべてが動き出しました。
インターンに参加することが目的ではなく、そこで何を感じ、どんな仮説と答えを持ち帰れるかが就活の本質です。1社、2社と動くうちに、選考も自己分析も、すべてがリンクしていきます。「何がやりたいか分からない」と迷う人こそ、まずは動いてみてください。
その先に、予想もしなかった“志望度の確信”や、“自分の強み”が待っているかもしれません。前編から読む
...
会員登録して全ての内容を見る
続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。
外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。
この記事を友達に教える



