
クライアントの組織や人にまで向き合う。CDI独自の経営の全体像を意識したコンサルティングスタイル
Sponsored by コーポレイトディレクション
2024/06/07
会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
sponsored by コーポレイトディレクション

コーポレイトディレクション(CDI)は、1986年「日本企業の真の変革」を目指し、外資系戦略コンサルティングファームであるボストン コンサルティンググループ(BCG)からスピンアウトして設立された、日本初の独立系戦略コンサルティングファームだ。
今回は、代表取締役の小川達大氏から会社設立の背景やCDIの特徴を、新卒入社の新谷慈氏と望月花氏から他コンサルティングファームとの違いやここで働く醍醐味(だいごみ)を語ってもらった。コンサルタントに必要な「経営者と向き合う力」を、若手時代から得られる環境がCDIにある。
※内容や肩書は2024年6月の記事公開当時のものです。
外科治療だけでなく、漢方治療も行う病院のようなコンサルティング
――CDIの成り立ちについて教えてください。
小川:CDIは1986年に、国内初の独立系経営・戦略コンサルティングファームとして設立されました。当時の日本には外資系のコンサルティングファームしかなく、アメリカで開発された経営の考え方やスタイルをベースにした支援が行われていました。もちろんそこから学べることはたくさんある一方で、日本企業には日本ならではの特性や考え方もあるものです。そこで、「日本企業の課題に向き合える、外資系でも日系でもないコンサルティング会社をつくりたい」と、外資系コンサルティングファーム在籍の10人がスピンアウトする形でCDIを立ち上げました。
われわれのコンサルティングスタイルは、例えるなら“外科治療だけでなく、漢方治療も行う病院”のようなものです。企業とは人間の集合体であり、経営は人の営みですから、白黒はっきりつけられない問題もたくさんあります。その中でも企業や経営をより良くしていくには、一歩ずつ前に進む決断をしていくことが必要なんですよね。その決断を支援し、漢方治療のように内側から人や組織を変えていく向き合い方を大切にしています。
――CDIの事業上の強みは何ですか。
小川:CDIの強みは2つです。1点目は、経営の全体像を意識した支援を行っている点。一般的なコンサルティングファームは一部の機能やテーマを切り出して案件化するのが通例ですが、実際に経営者が何かを決断する際は、全ての機能やテーマを総合的に見なければなりません。つまりプロジェクトが個別に動いているだけでは、機能やテーマ同士が対立することもあるんですね。そのためわれわれは、会社全体を見据えた機能横断・テーマ横断的な支援にこだわっています。
2点目は、リアリティーのある解決策を提示する点。いわゆる戦略コンサルティングファームは、実現可能か否かにかかわらず、事実に基づく分析と論理的思考を基にした解決策を提示することが多いものです。そのような提案が必要な場面もありますが、われわれは地に足を着けた解決策を提示したいと考えています。論理的に正しいかどうかよりも、確実に一歩前進できる策を提示するのが当社です。これは良しあしというより、スタンスの違いですね。
コンサルタント一人一人の“人格”で提案する
――CDIが掲げる理想のコンサルタント像について教えてください。
小川: 白黒つけられない問題への決断も支援し、クライアントの前進を促すことを大切にするコンサルティングを行うためには、仕事や人生を通して「人格を発展させること」が不可欠だと思います。
とある外資系戦略コンサルティングファーム出身のメンバーが驚いていたのですが、CDIの提案資料にはよく「主観」が入ります。そのメンバーがいたコンサルティングファームでは、どんな説明も客観的事実に基づいて行うべきであって、いちコンサルタントの主張はノイズでしかないというのが常識だったようなんです。しかしわれわれは、各コンサルタントの主張こそが最重要だと捉えています。経営者と意見を交わすことで方向性がつくられ、そのプロセスを通じて経営者が決断できる状態になっていくのです。このような支援の仕方だからこそ、自身の生き方や考え方が全て仕事に投影されることになります。
人格を発展させるには、仕事に全身でぶつかることが大切です。壁が立ちはだかることもあると思いますが、そこでしっかり相手と対話して大変さを味わうと、いろいろな景色を目にできるはずです。そこで自分なりに解釈したことが血肉となり、人格をつくっていくのです。

――CDIでは一人前になるまでにどれくらいの期間を要するのでしょうか。モデルケースがあれば教えてください。
小川:前提として、CDIには「UP or OUT(昇進か、さもなくば退職か)」という発想は全くありません。本人に意欲がある限り、当社で一緒に働いてほしいと考えています。
その上で、一人前(マネージャー)になるまでの期間は人それぞれです。新卒で入社して5年弱で独り立ちする人もいれば、8年以上かかる人もいます。そこに優劣はないというのが、当社の考えです。独り立ちまでに長い時間を要した人だからこそ見える景色があるはずですし、その景色がまたその人自身を育てますからね。付け加えると、それが当社のバラエティーにもつながっていくのだと考えています。
――クライアントと新規事業開発のジョイントベンチャーを立ち上げている点も特徴ですが、この取り組みはどのような目的で行っているのでしょう。
小川:先ほど「漢方治療的なコンサルティングを大切にしている」と話しましたが、会社は内部にいる人の意識やスキル、経験が変わることで、大きく前進するものだと思っています。そして、ジョイントベンチャーはそれを実現するための場だと捉えています。
既存の組織とは違う場所で事業開発をすると、やはり人は変わっていきます。その人が既存組織に戻ると、今度はその組織や会社全体のアイデンティティーも少しずつ変わっていくんですね。事業開発を行いながら、人も変えていく共有地。それが、われわれの目指すジョイントベンチャーです。
クライアントは、共に「解」を求めるパートナー
――ジョイントベンチャーでは、どのような事業開発支援をしていますか。
新谷: 一例として、BtoBオークション、リユース・リサイクルの事業を展開するオークネットと一緒に立ち上げた「ストラテジックインサイト」があります。同社はオークネットの新規ビジネス領域の開拓を目指し設立しました。
現在進めている事業は、「Selloop(セループ)」という二次流通支援サービスです。顧客流出や購買機会の減少といった事業課題を抱える企業やこれまで二次流通領域に参入するのが難しかった企業を対象に、新たな商品の循環を創出し、顧客との接点とつながりを深める流通支援をしています。
私は入社2年目の時から他のプロジェクトと並行して6年ほど担当しているのですが、事業戦略立案から立ち上げ、運用、実行、検証までの事業推進の一連に携わらせてもらいました。事業運営責任者のような立ち回りをしており、業務範囲は広く裁量はかなり大きいです。

――社員目線でのCDIの特徴や働く魅力について教えてください。
望月:CDIの大きな特徴は、師匠が弟子を採るような“徒弟制”を導入している点です。一般的なコンサルティングファームでは2〜3年在籍したら起業や転職のキャリアを考える人が多いと思います。しかしCDIには、一人前のコンサルタントになるまで師匠が見守ってくれる環境があるのです。就職活動中にこの話を聞き、私は後者の環境で頑張ってみたいと思いました。
また私の師匠にあたるマネージングディレクターが、選考の際に将来を真剣に考えてくれたのも印象的でした。選考中であるにもかかわらず、私にどんなキャリアがマッチするのかを一緒に考え、CDI以外の選考を受けることも勧めてくれたんです。「CDIに入社したら、クライアントの課題解決のために親身になって働けるんだろうな」とイメージができ、CDIへの入社を決めました。
新谷: クライアントとの関係性が、“先生と生徒”でも“資料納品者と受領者”でもなく、一緒に解を出す“パートナー”であることが、CDIの大きな魅力です。他社でもいえることかもしれませんが、CDIの場合はそこに大きなこだわりを持っています。
「課題に対する答えを提供する」「業界の知見やノウハウを渡す」といった一方的な支援ではなく、挑戦しがいのある仮説をクライアントと双方向的に考えていくことができるんです。上場企業の経営者など優れたビジネスパーソンと同じ目的に向かって議論ができるのは、CDIのユニークな魅力だと思います。
スキルだけでなく、人間力の向上を重視
――新卒で入社したメンバーが、上場企業の経営者と肩を並べて議論するまで成長できるのはなぜでしょうか。
望月:CDIでは「あなたはこの能力が足りないから伸ばして」といった、丸バツをつけるような指導や評価を基に、本人の意思に反したプロジェクトや働き方を押し付けることはありません。どんな能力を身に付けるかは本人の自由であり、その人なりの伸び方があるという考えが根底にあるのです。そのため“失敗して叱られる”という大変さよりも、自分で自分にプレッシャーをかける大変さの方をよく感じますね。
言い換えると、自分自身の感性が閉ざされることなく成長していける環境がCDIにはあると考えています。クライアントからすると、上司や先輩と同じようなことを語る人よりも、自分なりの考えを述べる人の話の方が、聞く価値があると思うのではないでしょうか。

新谷: もちろん細かい指導やサポートが全くないわけではないですが、あえて抑制している部分は確かにあると思います。CDIのコンサルタントはクライアントと直接議論して最適な方向性を探っていくことが仕事のため、「ノウハウやフレームワーク通り進めればうまくいく」というものではないんですね。いわば総合格闘技のようなものだと思います。そのため、結局はその人自身の力で育っていくことが求められるのかもしれません。
そのため組織としては属人的かつ非効率な部分があるのですが、それもCDIの魅力の一つです。効率性を求めてコンサルティングの手法をフレームワーク化してしまうと、クライアント固有の状況や問題に対処しきれなくなったり、微妙にゆがんだ回答となってしまったりする可能性がありますよね。その点CDIは簡単に答えを出すのではなく、各クライアントに寄り添い、一緒に悩むことを重視しているのだと思います。
結果的にCDIでは、スキルの集積や組織の中でうまく動く力ではなく、自律的に活躍できる人格が鍛えられていきます。
――これからどんな人と一緒に働いてみたいですか。
望月:一言で言えば、柔軟な人ですね。CDIでは、最短経路で物事を解決することに固執せず、クライアントの思いや状況を踏まえた解決策を導くために議論することも多いんです。このような仕事を楽しめる人と、一緒に働いてみたいです。
新谷:考えることが好きな人と一緒に働きたいです。そして“素直さ”と“生意気さ”をバランス良く併せ持つ人は、とても向いていると思います。CDIでは、上司やクライアントにガツガツ当たっていく勇気がとても大切なのですが、一方で「自分の考えだけに執着せず、相手の考え方の背景にも思いをはせてみる」という素直さがあると、さらに成長できると思います。
上下関係は厳しくなく、師匠や上司との距離がとても近いんです。普段の何げない会話や業務など、日々のやりとりから得られることも多く、自然と人間力を向上させられる環境が、CDIにはあります。
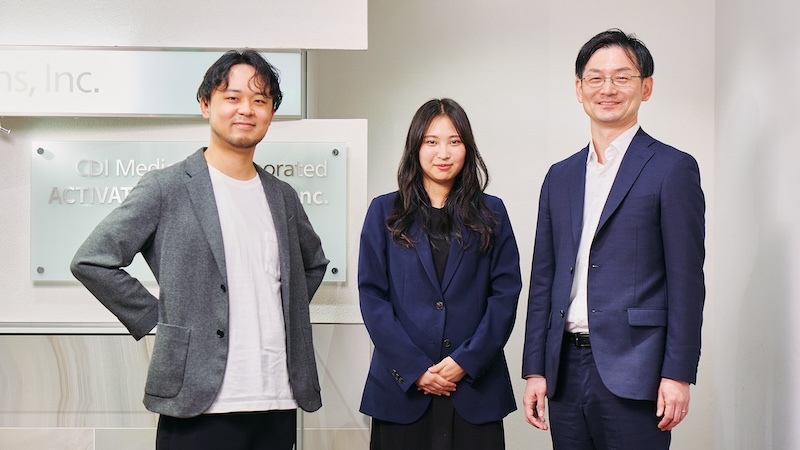
この記事を友達に教える


