
会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
sponsored by 三菱UFJリサーチ&コンサルティング

政策立案のためのデータ分析から企業の人材戦略まで、幅広い社会課題に取り組む三菱UFJリサーチ&コンサルティング(MURC)は、シンクタンク部門とコンサルティング部門で「部門別採用」を実施している。新卒入社でも配属を運に任せることなく、希望する領域で専門性を磨いていくことができる。
今回は、シンクタンク部門の政策研究事業本部の小林庸平氏と大熊丈士氏、コンサルティング事業本部の佐藤文氏に、部門別採用だから実現できるキャリアや、公共と民間の両視点から新たな社会的価値の創造に挑戦するプロジェクトについて話を聞いた。
※内容や肩書は2025年6月の記事公開当時のものです。
部門別採用がもたらすキャリアパスの安心感
──MURCはシンクタンク部門とコンサルティング部門を併せ持っていますが、どのような組織なのでしょうか。
小林:人数や売り上げ面ではコンサルティング部門の方が大きいものの、シンクタンクらしさが色濃く残っている組織です。多くのコンサルティングファームでは、パブリックセクターもコンサルティングの1ドメインと位置付けられますが、当社は「政策研究」が部門として独立しており、シンクタンクとしての専門性を大切にしている会社だと思います。
佐藤:官公庁、民間企業の両方のコンサルティングを行う会社は多数ありますが、社内でシンクタンク部門が独立しており、学術的な専門性と実務的な応用力を持っているのが強みです。また、コンサルティング部門とシンクタンク部門との共同プロジェクトや、三菱UFJフィナンシャル・グループ内で協働する機会があるのも当社の特徴です。
──希望部門に配属される「部門別採用」は、学生にとってどういうメリットがあるのでしょうか。
大熊:配属リスクが少なくなります。私自身、就職活動の際に、関心がある分野にそのまま入っていけることに安心感を覚えMURCを選びました。
学生時代は「政策立案の際にデータを使った客観的な要素を入れられないか」ということに関心を持っていました。政策は多様な市民の声を反映することが重要ですが、時にはデータによる客観的な検証も必要です。MURCではそういった分析ができる環境があり、自分の興味に合致していました。

政策立案支援とクライアントの課題解決、両部門の役割
──シンクタンク部門の仕事について教えてください。
大熊:私の場合は、データを使った調査・分析が中心です。最近はビッグデータを活用できるようになり、官公庁から提供されたデータなどを分析して、属性ごとの違いを見たり、政策の効果を検証したりしています。MURCには、若手を積極的に成長させようとする文化があるため、クライアントの前で話す機会を与えられたり、プロジェクトの一部を任せてもらったりしています。
──どのようなクライアントとやりとりをするのでしょうか。
大熊:クライアントは官公庁の担当者で、30代前半の課長補佐クラスの人たちが多い印象です。現場で実際に政策立案に携わっている人たちと直接やりとりができて、貴重な経験を積めていると感じます。
──コンサルティング部門はどのような仕事を行うのでしょうか。
佐藤:コンサルティング事業本部は、戦略コンサルティングやデジタル、サステナビリティーなど、さまざまな分野でクライアントの課題解決に取り組んでいます。人事コンサルティングの組織は比較的大きいですが、入社後は多様な分野を経験できる仕組みになっています。
私はHR第1部に所属し、人事関連のコンサルティングを行っています。具体的には従業員や役員向けの評価制度などの見直し、トレーニングプログラムの提供などです。最近では人事領域でもデータ活用が進んでいるので、データアナリティクスのプロジェクトも増えてきています。
高度な専門性と誠実なコミュニケーションが息づく
──組織文化について、特に印象的な点を教えてください。
佐藤:当社は専門性の高い人が多いにもかかわらず穏やかな雰囲気があり、クライアントからも付き合いやすいと評価されることが多いですね。礼儀正しさを大切にしながらも、風通しの良い組織です。
10人程度の小さな組織に分かれており、相談しやすい体制になっているため、チーム内でのコミュニケーションもスムーズです。こうした環境が、互いに意見を言い合える土壌を作っていると感じます。

──風通しの良さを感じる具体的な場面は。
大熊:インターンシップの際に、若手研究員がベテラン研究員とフランクに議論している光景を目の当たりにし、驚きました。そして、風通しの良さは、入社後の今でも実感しています。自分の専門分野について発信すると、一人の研究員として意見を尊重してもらえます。「研究員はこうあるべきだ」という単一の価値観を押し付けられることなく、自分の考え方を大切にできる環境だとも感じています。
──キャリア形成や専門性を深める制度についても教えてください。
小林:専門性を身に付けていくと、少しずつ指名で仕事を依頼される機会が増えていきます。若手の研究員は先輩のサポートから始まりますが、一定の経験を積むことで自分の関心領域を深めていくことができます。
シンクタンク部門には、ある程度経験を積んだ研究員が活用できる「選択年俸制」というユニークな仕組みもあります。これは、自身が出す成果をコミットし、年収を選択できる制度です。私自身も仕事をしながら博士課程に通うためにこの制度を活用し、それまでよりも低めの成果・年収を設定し、勉強・研究時間を確保しました。子育ての時期などに仕事の量を減らすこともできます。こうした柔軟な働き方ができるのは魅力だと思います。
部門横断で社会課題に挑む行動科学チーム「MERIT」
──シンクタンク部門とコンサルティング部門の協働プロジェクト、行動科学チーム「MERIT」の活動はどのようなものでしょうか。
小林:行動科学チーム「MERIT(Murc Experimental and behavioRal Insights Team)」では、人間の非合理的な側面を理解し、より望ましい行動を促すアプローチを研究・実践しています。
例えば、健康のために運動したいと思っていても先送りしてしまったり、資産形成の重要性を理解していても行動に移せなかったり。こうした人間の行動パターンに「ナッジ※」という小さな後押しを与えることで改善できないかと研究しています。
※ナッジ:選択の自由を保ちながら、環境設計や情報提示の工夫によって人々を望ましい行動へ誘導する手法
──ナッジによる行動変容は具体的にどのような場面で応用できるのでしょうか。
小林:公共領域で応用できると考えています。例えば、宅配便の再配達問題の解決やがん検診の受診率向上ができると考え、実証実験などを行っています。他にも省エネ性能の高い家電製品の購入を促すための情報提供の実験なども実施しています。
MERITの取り組みは、部門を超えたチームを結成できる「事業開拓組織」という仕組みを使って実現しています。会社からは活動費も支給され、自治体との実証実験などには追加の支援も受けられます。

── 一見すると業務負荷が増えるものに見えますが、どういう意義があるのでしょうか。
小林:こうした投資的活動は短期的には業務量が増えることもありますが、長い目で見ると専門性の強化や新たな案件の創出につながります。長期視点で新しいことに挑戦し続けられる環境が整っていると思います。
佐藤:人事分野では働き方改革や健康経営(健康診断受診率向上)、新型コロナウイルス禍後のコミュニケーション活性化など、行動科学の知見を生かせる領域は多いと考えています。
両部門の専門性を組み合わせることで、新たな価値を生み出せることは意義があると感じています。
──若手でも部門横断的な取り組みに関わる機会はありますか。
大熊:もちろん通常業務をしっかりこなした上での活動になりますが、自分で関心を持った課題に取り組む姿勢を会社も全力で応援してくれます。
「新しい価値を創造する」MURCが求める人材
──シンクタンク部門とコンサルティング部門には、どのような人材が向いていると思いますか。
小林:シンクタンク部門には自主性を重んじる組織文化があるので、“自分の名前”で仕事をしていきたい人、新しいことに挑戦していきたい人が向いています。言われたことを忠実に実行するタイプよりも、自分で道を切り開こうとする人に適性があると思います。
データの活用範囲が広がり、分析ツールも進化する中で、データ分析によって対応できる問題の範囲も広くなっています。その中で、社会的に認知される前の課題に光を当て新しいアプローチを提案していく活動が、やりがいにつながっていくのではないでしょうか。
佐藤:コンサルティング部門では、やりたいことがある人、仕事に集中できる環境を求める人が向いています。さまざまな業界に関わることができるので、自分の得意分野や関心領域を見つけていくこともできます。
──キャリアの観点で、今後どういう未来を描いていますか。
大熊:私は研究員として、政策立案におけるデータ活用の実践的なノウハウを蓄積していきたいと思っています。データ分析自体はそれほど難しくなくても、そのタイミングや伝え方、政策への反映方法など、実践的なハウツーは複雑です。自分がリードする案件でそうした経験を積み、政策立案におけるデータ活用が持つ意味や実践における注意点・意識すべきことなど、「こうあるべきだ」という考えを形成し、発信していけるようになりたいですね。
佐藤:コンサルタントとして既存の人事コンサルティングサービスを提供しながら、行動科学のような新しい領域にも挑戦していきたいと考えています。MURCにはそうした新しいチャレンジを応援する風土があります。
──最後に、MURCならではの強みは何だと思いますか。
小林:自由度の高さと専門性の深さが共存していることだと思います。当社では入社後、経験を積むにつれて自分の専門分野を確立していく環境があります。 また、新しい取り組みへのサポート体制も充実していて、研究員とコンサルタントが垣根を越えて協働できるカルチャーがあります。それぞれの専門性を持ちながらも、組織の壁に阻まれることなく新しい価値を創造していける点が、MURCの大きな強みだと思います。
大熊:若手でも早い段階から責任ある仕事を任せてもらえる文化と、年次や役職に関係なく意見を言い合える風通しの良さが特徴的です。互いを尊重する空気があり、それが多様な視点からの問題解決を可能にしているのだと思います。
佐藤:シンクタンク部門とコンサルティング部門が協働できる環境は、当社の特徴といえると思います。行動科学チームのような取り組みも、両部門の知見を生かして社会課題の解決に挑戦する場となっています。自由さと責任のバランスが取れた環境の中で、真のプロフェッショナルとして成長できる組織だと感じています。
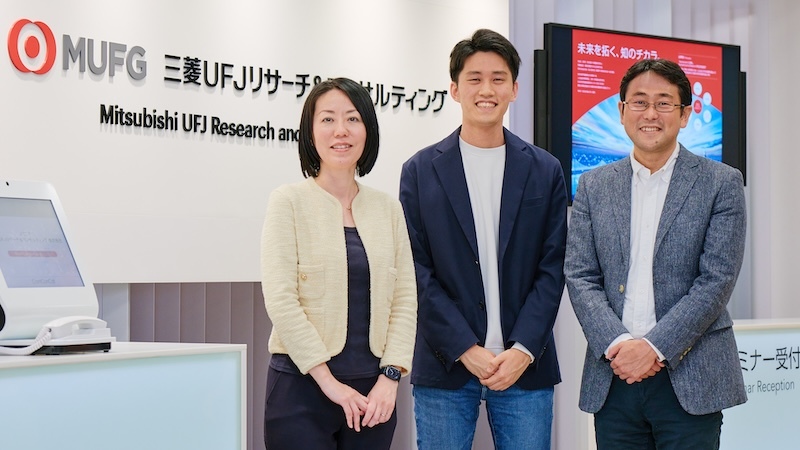
この記事を友達に教える



三菱UFJリサーチ&コンサルティング



