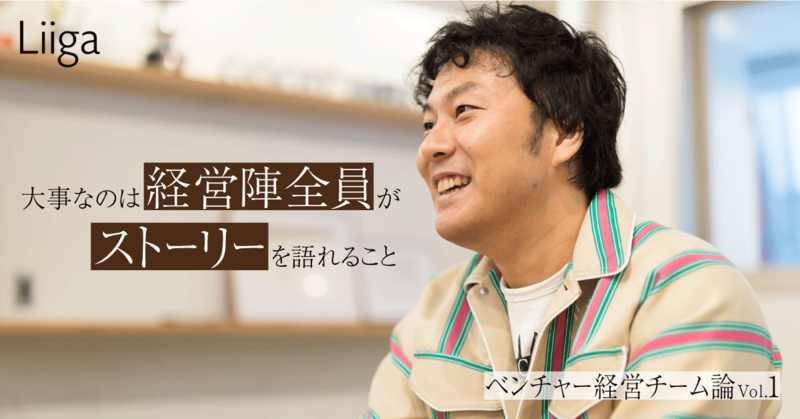会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
presented by Liiga
創業者の力には限界がある。ベンチャー企業の飛躍には、成功を呼び込める“強い”経営チームが不可欠だ。ただ、チームづくりは難しい。起業家は、いつ、どんな人材に参画してもらうべきか、逆にCxO転職を目指す人材は、どう新天地を選ぶべきか-。幾多の創業・成長プロセスに関わってきたベンチャーキャピタル(VC)関係者らに、経営チームづくりとCxO人材のキャリアを問う。初回はANRI代表パートナーの佐俣アンリ氏。
「Liiga」では、皆様の少し上の先輩である若手社会人に向けたキャリアコラムを展開しております。本日は皆様が就活を終了した後に見える世界を、少し先にお届けします。
・「たとえ年収が半分になっても、経験を“買い”たかった」。私が年収3,000万円のポジションを捨て、上場企業のCxOに転職した理由
・ゴールドマン・A.T.カーニー出身CFOに聞く「スタートアップのCxOになれる人・なれない人」【ハウテレビジョン執行役員との特別対談・前編】
・外銀とベンチャーは異世界―。元ゴールドマン「東芝問題」担当の試練と成長 外資投資銀行→CxO転職の光と影Vol.4 ビザスク・瓜生英敏COO
・強さ際立つラクスルの経営チーム。創業期CxOの“つまらなさ”を越えて
・仮説検証が苦手な商社マンは創業期向き!?コンサル出身よりフィットする理由
・今CxO集めで強いのはあの会社。メルカリ譲りの徹底した戦略
・金融、コンサル、商社の“村”に浸かるリスク。人脈広げ情報を得よ
ANRI代表パートナー
慶應義塾大学経済学部卒業後、株式会社リクルートに入社、イーストベンチャーズ株式会社を経て2012年にANRIを設立。
独立系ベンチャーキャピタルとしてインターネット・ディープテック領域約100社に投資を実行。シードファンドとして300億円規模のファンドを運営中。 主な投資支援先としてラクスル、hey、UUUM、ミラティブ、スマートドライブ、クラウドワークス、コネヒトなどがある。
強さ際立つラクスルの経営チーム。創業期CxOの“つまらなさ”を越えて
――数々のベンチャー企業を支援してきた立場から見て、優れた経営チームの条件とは。
佐俣:経営陣全員が、自社の成長ストーリーを何も読まないで語れることですね。COOなら社員や顧客に対して、CFOなら金融機関や投資家などに対して、どんな時でも雄弁と自社の未来を語れるべきです。逆にこれができない人だと、それまでいかに華やかなキャリアを積んでいても、ベンチャーCxOとして全く活躍できなかったりします。
例えば、ラクスルは非常に良いチームだと思います。5人の主要な経営メンバー全員が、自社がどんな夢を描いているかなどをメディア、イベント、SNSなどを通じ発信し続けています。ベンチャー企業にCxOとして入社する場合、その企業の世界観を最低2000字くらいで即座に記事などに書けるようでないと、新天地で輝けないと思った方が良いでしょう。
実は投資銀行出身CFOで「金融周りはプロだけど、会社の成長戦略は自分にはあまり関係ない」といったスタンスの人も結構います。ですが、CFOが成長ストーリーを語れないので投資家相手にいつもCEOが前に出ているというのは、あまり良い状態とは言えません。
――ステージによって経営陣の役割も変わりますね。
佐俣:創業期のCxOは、ある意味ですごくつまらない仕事をやらなければならないことが多々あります。CFOだったら、たいてい最初にやるのは領収書の整理です。もしくは勘定科目を考えることでしょうか。投資銀行での経験や公認会計士のスキルなどは、全く求められません。
ラクスルでCFOを務める永見世央さんが入社して初めてやった仕事の1つは、女性従業員向けにお菓子を発注することだったようです。みずほ証券のIBD(投資銀行部門)、カーライル、DeNAと渡り歩いた永見さんでさえ、こんな感じです。永見さんの素晴らしいところは、そういうことを嫌がらず淡々とこなしたことでしょうね。本当の意味でのプロフェッショナリズムと言えます。
――永見さんのように金融、コンサル、ファンドなどいわゆるプロフェッショナルファーム出身の人がベンチャーCxOになる例が増えています。
佐俣:創業期のベンチャーの場合、プロフェッショナルファームで培ったスキルは当面全く生きないと覚悟した方がいいでしょう。3年くらいはスキルをほとんど生かせず、あとは“仕事をやり切る力”でなんとかする覚悟です。それが無理ならば、創業期ではなく成長期のベンチャーを選ぶべきです。その企業のフェーズを見て、「これなら参画できる」と冷静に判断する力が問われます。
金融出身のCFOだったら、数十億円の調達をするようになる辺りからは経験が生きてきます。機関投資家と話す機会が一気に増えますから。従来はIPO(新規上場)が変わり目になることが多かったのですが、最近はラストラウンド(IPO前の最後の資金調達)で機関投資家を相手にするケースが増えているので、転換点は早まっている印象です。
また、気を付けた方がいいのは、創業者がプロフェッショナルファーム出身でない限り、ベンチャー側も金融やコンサルの人の採用に慣れていないということです。例えばゴールドマン・サックスから人が来た場合、「経理も財務も労務も全て分かる人」と勘違いされがちです。
仮説検証が苦手な商社マンは創業期向き!?コンサル出身よりフィットする理由
――商社出身の人はどうでしょうか。
佐俣:商社の人は実は創業期にすごく合っていると思います。転職の時点で30歳以下であり、商社の世界に浸かり切っていないことが条件ですが。特徴は、仕事がすごくできる半面、仮説検証は苦手なことです。仮に5つの選択肢がある場合、全てを検証する前に1つをまず進めてしまう感じですね。
もう1つの特徴が、資料がきれいではないこと(笑)。これは創業期に合っています。コンサルの人だったら資料をきれいに作って5つの選択肢全てを検証しがちですが、それだとリソースが足りない創業期には向いていません。仮説検証は巨大な組織で意思決定する時に生きるやり方です。
商社にいると、例えばですが「明日からイスタンブールに行って何でもいいから売り上げを作ってこい」みたいなプロジェクトを経験したりするわけです。起業に似ていると思います。もちろん商社のネットワークなどがあるので完全にゼロからのスタートではないものの、本質的にやることは変わりません。「とにかく前に進めないといけない」という状況を経験していることは、創業期のベンチャーに行くとすごく生きます。
我々が投資している名古屋大学発医療ベンチャーのIcariaは、同大学出身の研究者と元商社マンが共同創業したのですが、すごく良い組み合わせだと思います。技術は確立しているのですが、他方でいろいろな所に“突撃”して売り込まないといけないため、商社マンの物事を前に進める力が生きてきます。
逆に言えば商社マンに成長期以降で生きる専門的なスキルがあるわけではないので、創業期からジョインした方が絶対に楽しいと思います。商社の人は皆さん基本的に優秀なので、たいていどんなCxOポジションでもいけるはずです。商社時代に金融・財務関連の仕事に携わっていたならば、CFOでも大丈夫でしょう。
だからこそ、商社の人にはもっとベンチャーに飛び込んでもらいたいですね。まだまだ少数派だと思います。特に(現実の社会課題をIT技術などで解決に導く)「リアルテック」のビジネスが増えているので、活躍機会が広がっていると思います。リアルテックで深く関わることになる製造業など伝統的な産業は独特の世界観があり、商社マンは結構そういう分野に慣れているからです。ANRIでパートナーを務める鮫島(昌弘氏)も元商社で、在籍時は飲料メーカー相手に脱脂粉乳を売り歩いていました。この手の仕事に慣れている人は、この先もっと光ると思います。

――メガベンチャー出身者はいかがでしょう。
佐俣:フェーズにもよると思いますが、メガベンチャーの人も面白いと思います。例えばheyは従業員200人くらいのフェーズですが、主力2事業を率いている2人が、いずれもサイバーエージェント出身者です。サイバーエージェントの人はあらゆる案件を“拾う”ガッツと、短期的にうまくいかなくても動き続ける胆力が圧倒的です。heyみたいなフェーズなら最適でしょうね。
事業を一気に成長させるなら、グリーのような会社にいた人も良いと思います。ソーシャルゲーム関連をやってきた人だと、一気に決めてどんどん結果を出すことに慣れているでしょうから。ただ、事業探索フェーズだとやきもきしてしまうかもしれません。伸びると分かっているものを思いっきり伸ばしてきた人が多い印象です。
今CxO集めで強いのはあの会社。メルカリ譲りの徹底した戦略
――足下で経営チームづくりに関して注目している企業は。
佐俣:ミラティブは上手だと思います。GunosyのCFOだった伊藤光茂さん(現ミラティブCFO)や、セガゲームスのCSOだった岩城農さん(同CSO)など、良い人がどんどん入っています。
良い経営チームの条件につながるのですが、優秀な人を惹きつけるポイントも、自分たちの信じるストーリーを雄弁と語れることです。ミラティブはそのストーリーを、ネットを通じ積極的に外部発信しています。自社がどんな夢を描いているかに加え、社内はどんな環境であり、その中でどんな仕事をする人を「ハイパフォーマー」と位置付けているかみたいなことを、経営陣がSNSやメディアなどでひたすら語り続けるわけです。
そういう時代になっているのだと思います。ストーリーを語れないと良い人を採れない時代というか。ベンチャーの給与水準が全体的に上がり選択肢は増えているので、ストーリーが差別化要素になっているのかもしれません。
なので、本気の経営者は多くの時間を採用関連に割いています。ストーリーを語るにしてもメディアに出たり、自分で「note」に投稿したり、SNSで発信したりするなど、あらゆる手段でやり続けるわけです。それで興味を持った人が会いに来たら、徹底的に話し合うみたいな感じですね。ちょっとブログを1本書くとか、そんなレベルではありません。熱量と粘着性が違います。「あの会社すごく採用で結果が出ている」と周りが気づいたとしたら、その半年以上前から経営者が尋常ではない熱意で採用に取り組んでいることが多いと思います。
――ミラティブは「絶対良い人を採る」という執念すら感じますね。
佐俣:創業者である赤川隼一さん(同CEO)の強い意志でしょうね。数年前のメルカリがそうでした。みんなあの会社に採られていく、みたいな感じでしたよね。メルカリが際立っていたのは、狙った人に対して経営陣が素早く、あらゆる手段で徹底的にアプローチするやり方です。理想を絶対にあきらめない“すごみ”がありました。
ベンチャー企業の採用は間違いなくメルカリのおかげで進化したと思います。メルカリが、どんなことをやったかを結構公開してくれましたから。メルカリから別のベンチャーに移る人などによって、さらに進化するのかもしれません。
金融、コンサル、商社の“村”に浸かるリスク。人脈広げ情報を得よ
――CxO転職を目指す人が企業を選ぶ上でのポイントは。
佐俣:「こいつら面白いな」と笑えるかどうかに尽きます。ある本に「休日にスーパーマーケットで偶然見かけた時に話しかけたくなる人と、一緒に仕事をするべき」といった考えがあるのですが、私も本当にそう思います。特に創業期のベンチャーは大企業と比べ人と人の距離が近いですし、異動もないので人間的に好きになれない人と一緒にやっていくと、必ずつらくなります。そこは事前にしっかり見た方が良いかもしれません。
若ければ、3年くらいかけて自分に合っているか見極めるくらいの心持ちでも良いと思います。部外者が参加できるカジュアルな懇親の場を設けるベンチャーは増えていますから、積極的に参加し、社員とFacebookやTwitterなどでつながっておけば、情報が入るようになります。3年経ってその会社の空気の方が現職より心地よさそうならば、自然と足が向くはずです。
金融やコンサルなどの人がベンチャーに転職する例を数多く見ていますが、ベンチャー関連の友達がいる人の場合は、内情が分かるのでミスマッチはあまり起きません。一方、いわゆる「金融村」「コンサル村」「商社村」などにどっぷり浸かっていると、事前情報がないため、いざ転職するとびっくりしてしまうことになります。
さらに言えば、休日の夜とかだけでも、副業的にベンチャーの仕事を手伝うのが一番お勧めです。そうすると、いろいろなことが見えてきます。
あとは、かなり現実的な話になってしまいますが、その人と家族が生きていくのに最低限許容できる収入は結構明確な数字として決まるので、そのラインがどこになるかは意識しておくべきでしょう。そして、そのラインを無理やり下げるのは、良い選択ではないと思います。例えば、「ラインを越えたから子供の進路を変えないといけない」といった事態は、人生に余分なストレスを追加することになります。
そうした状況を乗り越えて成功した人もいますが、私の考えでは家族を犠牲にするべきではありません。だからこそギリギリ耐えられるラインを明確化した上で、配偶者などとよく話し“握って”から転職するのが現実的です。
いずれにせよ、情報を得やすくなっているのは良いことです。個人的に、人生において先が見えない状況での劇的な決断は、多くなくていいと思っています。劇的な決断をして成功した人が注目されがちですが、逆に失敗した人はメディアなどには出ないので、悪い例も多いはずです。
会員登録すると
このコラムを保存して
いつでも見返せます
マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事
P&G アクセンチュア
内定攻略 会員限定公開
トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム
この記事を友達に教える