会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
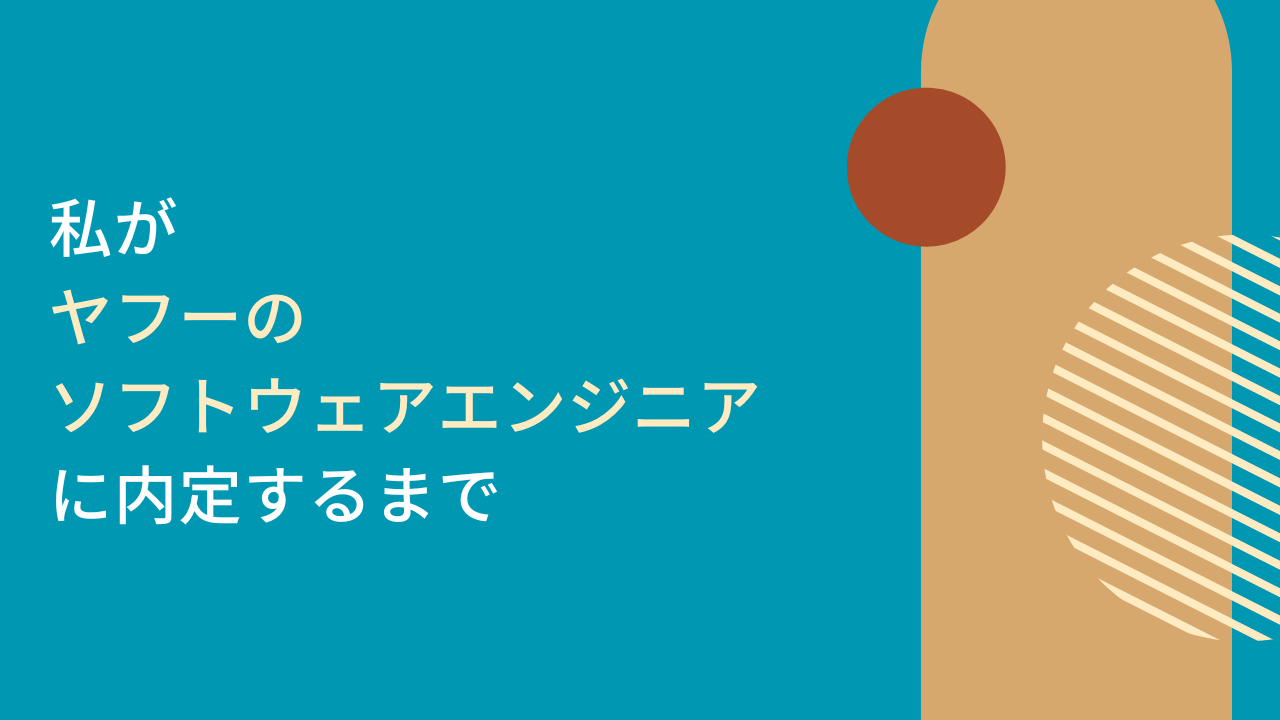
IT企業のソフトウェアエンジニア職を目指す方の中には「どういった対策をしたら内定できるの?」「プログラミングは大学から始めたけど大丈夫?」などといった疑問があると思います。
そこでヤフーのソフトウェアエンジニア職に内定した方に、これまでのプログラミング経験、選考内容、対策方法について寄稿いただきました!
自己紹介とこれまでのプログラミング経験
ヤフーのソフトウェアエンジニア職として内定をいただいた関東の国立大学院生です。自分の就職活動の経験が少しでも役に立つなら嬉しい、ということでこれまでプログラミング経験があるのか、内定をもらうまでのプロセスや対策がどのようなものなのか。また就職活動全般の対策についてお伝えできたらと思います。
まずプログラミング経験ですが、大学生になるまでは未経験です。高校生の時に漠然と「これから情報系の知識やスキルが求められるんだろうな」と思い情報系の学科を選び、そこからゼロから学んでいきました。
わりと「ソフトウェアエンジニア職に就く人は大学に入る前から経験している人ばかりでしょ?」というイメージを持っている人は多いと思いますが(私もそうでした)、内定者の中にも大学に入るまで未経験の方は驚くほど多いので安心してください。ちなみに私のいる大学では体感として情報系の学科でも、大学以前にプログラミング経験がある人は半分程度でした。
一般的な情報系の学科のように授業でC言語を軸に基本的なところから学び、3年生からは研究に伴い必要な知識・スキルを身につけていきました。1年生の頃はやはり未経験という事もあり、先生が言っていることを理解することができませんでしたが、経験のある友人に聞くことで乗り越えていました。
向上心高く、趣味のような感覚で勉強したり、何か個人開発をしたり、ハッカソンに参加している分けではなく、授業をとりあえずきちんと受けることに努めました。ヤフーのソフトウェアエンジニア職に内定した今でも、決してプログラミングが得意という意識はありませんが「こんなにたくさんIT企業があるのだから、どこかには受かるでしょ」というマインドで受けましたね。
せっかくの就職活動の機会なので、ソフトウェアエンジニア職を特別視することなく果敢に挑戦してみるといいと思います。
学部1年:基礎から授業で学習。C言語でプログラミングを学ぶ。Ubuntuを使ってディレクトリの操作
学部2年:C++, Rubyを授業で扱う。CGの授業や、Web制作の授業などがあった。
学部3年:授業では主にPythonを用いて物理シミュレーションや機械学習による画像分類モデルの構築を実施。3年生からSIerのインターンに参加をし始め、Javaを主に扱う。また研究室ではPythonとRubyを利用。
学部4年~大学院:研究が中心でPythonとRubyを主に扱う。また大学院1年時にヤフーなどの日系IT企業でインターンに参加。
ヤフーのソフトウェアエンジニア職の選考について
選考ステップ
選考の流れは以下のようになります。私の場合インターンに参加したためか、コーディングテストや1次部門面接がスキップされたと思われます。インターンに参加した人が全員スキップになるかは分からないです。
面接の雰囲気に関しては話しやすい空気感を面接官の側が用意してくれました。また選考ステップは全てオンラインで行われました。
面接の逆質問では「活躍している社員、エンジニアの特徴」「入社までにやっておくべきこと」「なぜYahooに就職することを選んだのか」などの質問を用意していて、適宜面接官の立場や年齢などによって変えました。
ES
ESに関しては複数の〆切があり、私の場合は一番最初の〆切で提出しました。どの〆切が有利などは噂ベースではありますが、実際のところどうなのかは分かりません。
内容としては「志望領域とその理由」「研究室でやっていること」「学生時代に頑張ったこと」「今まで触った技術」などでした。会社自体の志望動機はなかったと記憶しています。
コーディング試験(内容はインターン選考のもの)
こちらはオンラインで行われ、90分で3問程度出題されました。レベル感としてはAt Coderなどをやっていないので比較することはしにくいのですが、大学で4年間プログラムを書いていたら8割くらいは取れる問題という印象です。3問のなかで最後の問題は、計算量を意識したアルゴリズムがないと解けない問題となっていました。
制限時間があるので焦りは生じますが、焦らなければ解ける問題だと思います。大学時代の授業や研究をしていれば解けるはずなので落ち着いて取り組みましょう。
1次面接
こちら私はインターンに参加した関係で選考がスキップされました。基本的な質問に関してはESにあったような、「志望領域とその理由」「研究室でやっていること」「学生時代に頑張ったこと」「今まで触った技術」およびそれぞれの深掘りをされていたのではないかと思います。
2次面接
2次面接は30分間行われ、30歳前後の人事とエンジニア2名が面接官としていました。雰囲気はずっと優しく、やりにくさはなかったです。
聞かれた質問としては事前に知らされていた研究内容のプレゼンとその研究に関する質問でした。プレゼンは5分~10分程度でしてくださいと指定されていたので、研究で使っていたものをベースにスライドを作成しました。面接官は私の研究内容について専門外なので、なるべく分かりやすい言葉を使うことを心掛けました。
アドバイスとしては、普段の研究室や学会でのプレゼンよりも分かりやすく、極端にいえば小学生でも分かる内容にして話すことです。より専門的な話を面接官が聞きたい場合は、ちゃんと深掘りの質問をしてくるので問題ないと考えます。
最終面接
実質最終面接の3次面接は40代と思われる社員によって20分程度行われました。
聞かれた質問はとてもシンプルで「就職活動の軸は?」「どんな業界を見ているか?」「開発経験は?」という基本的なものでした。また「今の自分に足りないものは?」など少し私の中では難しい質問もありました。その際は少し時間をもらったうえで、しっかりと答えるように努めました。「どうしてその行動をとったのか?」など深掘りをかなりされるので、自己分析をするなど昔のことを思い出す、振り返るといいです。
就活の選考対策について
ES
エントリ―シートについては、就職団体などの学生に添削してもらうことがメインでした。外資就活ドットコム含め、いろんなサイトがエントリーシートの例を掲載しているので、それを参考にして1回作り、あとは添削をしてもらうことでブラッシュアップしていきました。
面接
面接に関してはとにもかくにも試行回数が大事と考えています。いろんな企業の興味のない企業を受けて練習していました。また就活団体の学生に面接官役をやってもらったりもしていました。面接の回数を重ねると、想定しない質問への対応力や回避能力が培われるので苦手な人ほど練習あるのみです。
後輩へのアドバイス
やりたいことがある学生に関しては、それが大きな原動力になると共に面接における説得力になるのでそれを軸にするといいです。私みたいに明確にやりたいことがない人は、やりたいことが見つかった時にいつでも動けるように準備できる環境にいることをオススメします。またとりあえずお金をある程度稼げることは生活の基盤を作るうえでも大切なので、重視してもいいのではないかと思います。
研究室で忙しい学生もいるとは思いますが、私の場合は研究に飽きたら就活の作業をして、就活の作業に飽きたら研究室をするというタイプでした。1つのことだけに集中しないと気が済まない人には難しいと思うので、自分なりの就職活動に向き合う方法を早急に掴むことをオススメします。
会員登録すると
このコラムを保存して
いつでも見返せます
マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事
P&G アクセンチュア
内定攻略 会員限定公開
トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム
この記事を友達に教える



