
私がAWSのクラウドサポートエンジニアに内定するまで
2023/12/22
会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
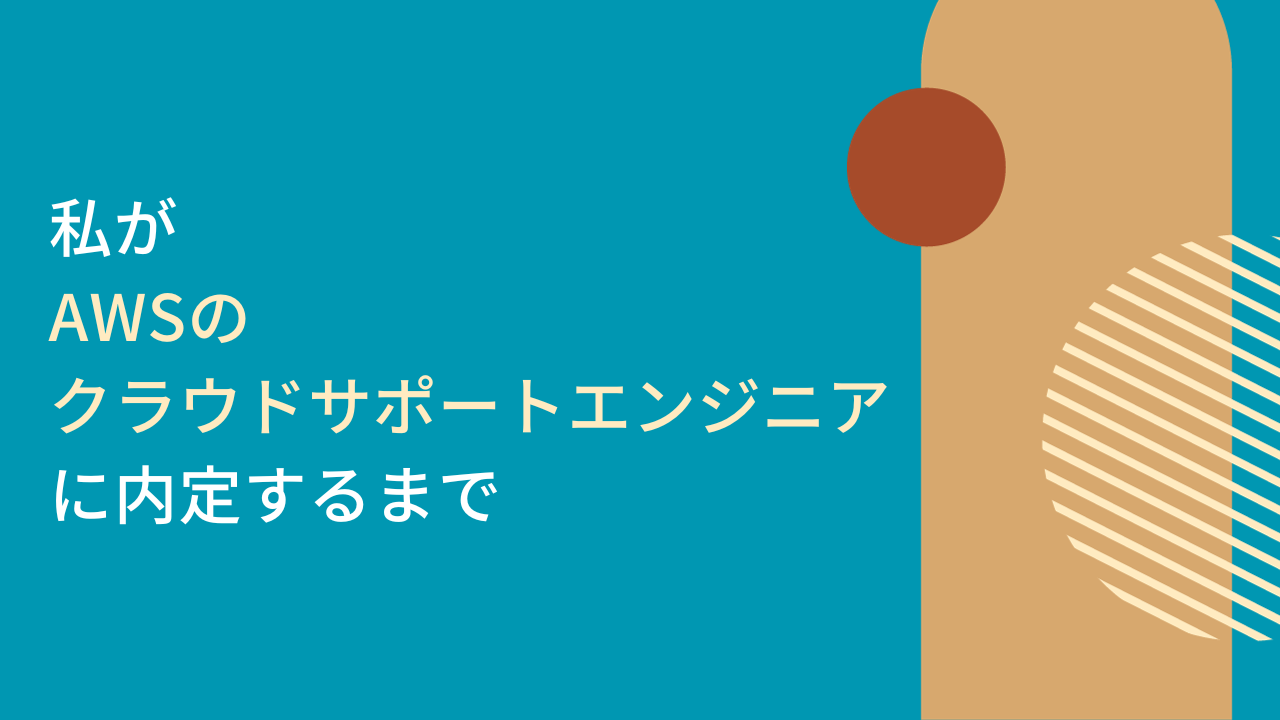
外資のIT企業への就職を目指す方の中には「どういった対策をしたら内定できるの?」「プログラミングは大学から始めたけど大丈夫?」「英語力はどのくらい必要なの?」などといった疑問があると思います。
そこでAmazon Web Service(AWS)のクラウドサポートエンジニアに内定した方に、これまでのプログラミング経験、選考内容、対策方法について寄稿いただきました!
自己紹介とこれまでのプログラミング経験
Amazon Web Serviceのクラウドサポートエンジニアとして内定をもらうことができた、都内の私大の大学院生です。本記事では私のプログラミング経験と内定をもらうまでのプロセスとその対策。またAmazon Web Serviceに限らず参考になるかもしれない就活の選考対策について書いていきます。
まずプログラミング経験ですが、大学に入るまで全くやったことがなく「食いっぱぐれがなさそう」という理由で情報工学科を選んだのが全ての始まり(と苦労のスタート)です。長期インターンや受託開発などは特に行ったことがなく、熱狂的なユーザーがいるAtCoderに関してもあまりやったことがなく、ほぼ経験はゼロに等しいです。
一方で情報工学科ということもあり、当然ですが大学の授業や研究を通してプログラミング経験を重ねていく環境。またコンピューターサイエンスについて学ぶ環境がありました。C言語のポインタでつまずくなど典型的な初心者でしたが、教科書や解説記事で理解を深め、実際にコードを書くことで理解していきました。
学部1年:プログラミングの基本を学ぶ。C言語で基本的な処理を学ぶ。
学部2年:アルゴリズムやオブジェクト指向(Java)を学ぶ。
授業のメインはCとJava、実験ではPython、R、MATLABを使用。
学部3年:プログラミングの授業はなく、実験で色々な言語(私は主にPythonを利用)で実装。後期では学生2名でペアになりチーム制作。Webのアプリケーションを作成。
学部4年:研究室に配属されC言語でシミュレーターを実装、解析でPythonを利用。
大学院:授業の課題をPythonで解いていた。また研究ではPythonとC++を利用。
AWSのクラウドサポートエンジニアの選考について
選考ステップ
私が体験した選考の流れはざっくりまとめると以下のようになります。
応募から内定まで3ヵ月ほどの期間がかかりました。比較的他のIT企業と比べると選考が行われるタイミングが早かったと思います。
アイルランド勤務のルートについて
...
会員登録して全ての内容を見る
続きは外資就活ドットコム会員の方のみご覧いただけます。
外資就活ドットコムはグローバルに活躍したい学生向けの就職活動支援サイトです。会員登録をすると、「先輩のES・体験記」や「トップ企業の募集情報リスト」など、就活に役立つ情報をご覧いただけます。
この記事を友達に教える


