
スタートアップのスピード感と大企業のスケール&パワーで世界の"不"をなくす。
Sponsored by エン・ジャパン
2018/11/15
会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
エン・ジャパンに「人材関連の広告と営業の会社」というイメージを持っている就活生も多いのではないでしょうか。実は、エン・ジャパンでは、テクノロジーで人事や採用のほか、新規事業で社会を変革していく取り組みが驚くほどのスピードで進んでいます。こうした動きをけん引する、デジタルプロダクト開発本部を統括する寺田輝之さん、エン・ジャパンのグループ会社で「インサイトテック」社長の伊藤友博さんにお話を伺い、エン・ジャパンの意外な素顔に迫ります。
目指すのは、求職者と企業の情報格差の是正
――エン・ジャパンに入社した経緯を教えていただけますか。
寺田:2002年に新卒で入社しました。当時、50人程度の企業規模の会社でした。大学の専攻はコンピューター関係ではありませんでしたが、ダブルスクールでデジタルやインターネットについて勉強していました。
インターネット関連の企業で働きたいと思い、ウェブで検索をしていたら、エン・ジャパンが、サイバーエージェントなどと一緒に検索結果として出てきました。運営していたサイトを見ると、とてもきれいに、使いやすいように制作してありました。これが入社を決めた理由の一つです。
入社後は、広告の営業担当になりました。営業はあまり志向していませんでしたが、「営業できない人が作るサービスは誰も売らない」と先輩から助言をもらいました。結局、お客様のことを知らずに作るサービスは誰にも受け入れられない、ということです。営業を1年間担当した後、ウェブサイトの企画・開発、マーケティングを手掛ける部署に異動しました。
――デジタルプロダクト開発本部で多くのウェブサービス立ち上げやリニューアルに関わるときに、心がけていることは何でしょうか。
寺田:当社サービスで扱っているのは、HR領域です。仕事は多くの人の人生において重要な要素です。多くの人が企業などに就職をして、1日8時間程度拘束されます。当社のサービスは、ある意味人生を決める意思決定に関わる重要な業務だと思います。
食べ物や服を買うという日常でよくあることについては、人間は経験を積み重ねることで、店の選定などをうまくできるようになってきます。ですが、就職や転職は、日本人の場合、多くて3回程度で、非日常です。経験が少ないうえ、選ぶ側の情報が圧倒的に足りないのが現状です。採用の最終的な決定権を持つ企業は、RJP(Realistic Job Preview)といって、求職者に事前に情報をきちんと開示する必要性が大きくなっている現在、この格差をどう埋めていくか、を常に考えながらサービスに関わっています。
――求職者と企業とで情報の非対称性があるということですか。
寺田:そうです。これは常に課題感として持っています。当社は、入社後、どのように活躍するかをサービスのゴールに設定しています。商品でいえば、購買がゴールではない。買った後、これをうまく活用できているかが重要です。求職者と企業で情報の非対称性が大きければ、入社後の活躍に影響が出てきます。
ゴールが異なるので、商品やサービスの作り方も変わってきます。当社の社員は、求職者が入社後に活躍できること以外は、サービスにおいては無価値だと思っています。他社と同様に、入社決定にフォーカスした商品を作ったり、マーケティングをすると社内から批判されます。
テクノロジーは、データドリブンに不可欠
――HR領域でも、テクノロジーの重要性は高まってきていますか。
寺田:はい。当社は、採用に加えて、教育や評価も事業の軸としています。入社後の適性テストなども実施していて、5年で115万人分のデータがあります。当社は職業や在籍している企業による価値観の違いや活躍度などのデータも持っています。テクノロジーは、データを分析して意思決定や企画立案に活用する「データドリブン」を実現するのに欠かせません。
入社から定着、戦力化までを意味する「オンボーディング」を支えるため、当社が関わってきた3000社の入社から離職までのデータを活用するにも、テクノロジーは不可欠です。
ウェブ系企業でウェブマーケティングをやっていた者や、ベンチャー企業でCTO(最高技術責任者)を務めていた者もいます。当社で、テクノロジーを駆使してデータをマーケティングに活用できているのは、こうしたバックグラウンドを持った社員が在籍しているからです。
事業を世界展開していくにも、テクノロジーは必要です。現在は、ベトナムやインドといったアジア中心となっていますが、北米でのサービスも視野に入れています。当社の方針が、採用の世界標準になればいいと思います。
――採用だけではなく、教育や評価も事業の軸としている理由を教えてください。
寺田:これらにミスマッチがあると、離脱する人が多いからです。企業が変われば、文化も変わります。入社してすぐに結果が出せるわけではありません。
また、中小企業やベンチャー企業を中心に条件に沿う人材の採用が難しい状況が続いています。譲れない企業カルチャーへの共感や最低限のスキル以外は、入社後身につけてもらうことになるため、成長を支援する教育制度がとても重要になってきます。
評価は、報酬を出す側である企業から一方的になりがちです。互いに納得できる評価を続けていけば、次の業務のモチベーション向上につながります。
一流のパートナー企業と議論、最新のマーケティングに接する機会も
――エン・ジャパンではどういう成長が望めますか。
寺田:私が本部長を務めるデジタルプロダクト開発本部は、プロダクトマネジメント、ウェブマーケティング、エンジニアリング、デザイン、コンテンツの編集業務など、多岐にわたる仕事で成り立っています。専門性を深めていくこともできますが、専門性が定まってない中では、様々な職種を経験できます。
また、当社の一流のパートナーと関わることで望める成長もあります。私は、グーグル本社のプロダクトマネージャーやエンジニア、ウェブマーケティング責任者と議論します。グーグルやフェイスブックなどグローバル企業と、最新のトレンドやテクノロジー、マーケティングなどを試せます。
また、他社ではなかなかできないことですが、当社ではメディア間異動と職種間異動の両方が可能です。例えば、「CAREER HACK」の編集業務をしているが、プロダクトを作ったり、マネジメント業務に携わるキャリアにチェンジしたり、マネージャーをしているが、実はデータ分析が得意だと認識して、データサイエンスのような業務を担当する、というようなキャリアも描けます。
ゼネラリストとしてのビジネスマンを養成したいという思いはあります。将来的にウェブサービスを立ち上げるとき、マーケティングやクリエイティブ、データなどについて知っておく必要があります。
プロフェッショナルとして、スキルと同時に、精神的な強さも身につけてほしいです。スポーツ選手でも、スキルはあるが、「ガラスのハート」と揶揄される人は、結果を残すことは難しいです。スキルと心が強くなっていって、結果的に報酬や権限の大きさにつながればいいと思います。
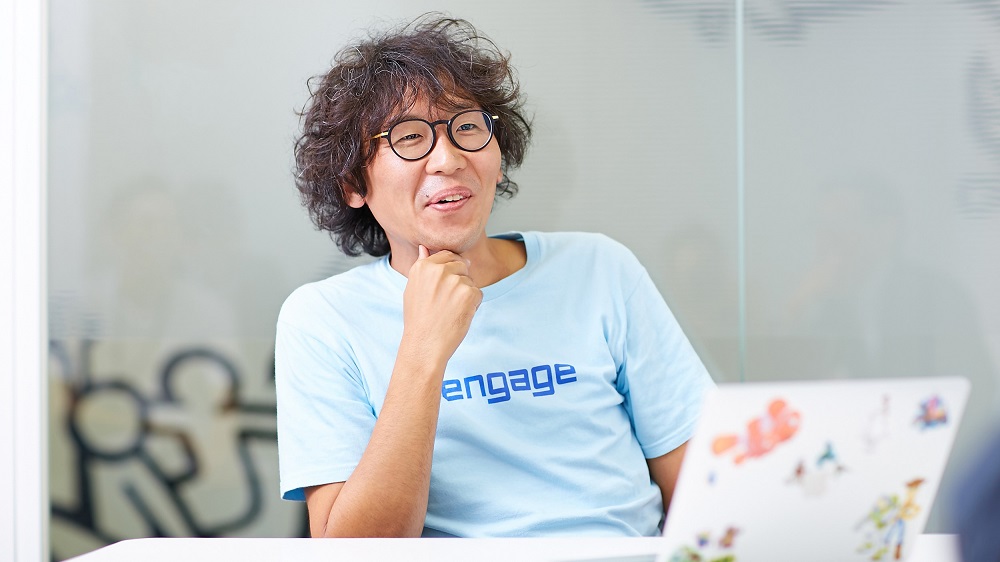
損得ではなく、善悪で動く人に来てほしい
――どういう人と一緒に働きたいですか。
寺田:損得ではなく、善悪で動くことができる人です。HRビジネスは、人生を左右します。善悪が何なのかを考えられる人でないと、人生を狂わせる可能性があるからです。
そのうえで、好奇心旺盛で、新しいことへの挑戦をいとわないことも重要だと思います。当社では、失敗はNGではありません。私は以前、ウェディング事業をやって負債を出すなど失敗もたくさんしていますが、そのたびに糧にしてきました。失敗こそ成長の糧です。成功だけだと成長もないし、学びもありません。

コミット度合いやスピード感…コンサルで感じた限界
――インサイトテックに入社した経緯を教えていただけますか。
伊藤:インサイトテックに入る前は、三菱総合研究所でビックデータを使ったマーケティングのコンサルティングや、人工知能(AI)を使った新規事業の開発、サービスの立案をやっていました。ある程度、責任ある立場で仕事をしていたのですが、シンクタンクでできる仕事のコミット度合いに限界を感じていました。コンサルとして顧客を支えてはいますが、どうしても、最後までやりきれない。新規事業をやるにも意思決定のスピード感も十分ではないと考えたことが、そもそも、ほかの会社に目を向けようと思ったきっかけです。
在籍している会社のネガティブなことを主張するくらいなら、外に出て自分の責任で事業を推進していこうと思うようになりました。

――新規事業そのものにもっとコミットしようと。
伊藤:はい。転職をするとき、軸としていたのが、自分の意思決定の範囲を広げたい、スピード感を高めて事業を成長させる中で、社会に貢献できるような存在になりたい、ということでした。
――起業は考えなかったのでしょうか?
伊藤:もちろん考えました。外資のパートナーと組んで起業するという選択肢や、IPO前のベンチャーのCFOというオファーもありましたが、それよりもいち早く世の中に価値を生み出したかったのです。それを成し遂げる手段として起業よりもふさわしいステージがあるなら、それもOKでした。
その中で、フォロワーではなく、自分が責任あるいは権限をもってやり切れるか、が他の選択肢との比較で当社を選ぶ決め手になりました。
データビジネスをずっと手掛けてきた立場から言うと、インサイトテック(旧社名「不満買取センター)が持っているデータは、世界で唯一。これを価値化するのは、データビジネスでキャリアを積んできた自分しかいないと考えました。
「不満はイノベーションの種」だと考えています。不満の中に期待があって、不満解決が新市場の創出につながると思います。当社に集まってくる「不満」は1日1万件。そのうち3割にアイデアや期待、提案などが入っています。これを新規事業に活かすことができるのです。
当時、「不満」という形で集まった日本語データのストックをいかにマネタイズしていくかという重要なフェーズに差し掛かっていました。いいはずだが売れない、売るための方法が確立されてない、といった課題を抱えていました。ジョインする段階としては恵まれていたと思います。
データが儲かる、と何となく言われていますが、データは、価値の源泉でしかありません。データだけでは、価値はないのです。課題を解決するために、データをどう活用するか、工夫が必要です。「Data is the next oil」と言われます。原油だけあってもあまり意味はなくて、ガソリンやプラスチックに形を変えて、使えるようにすることで初めて、原油の価値が出ます。データもまったく同じです。
不満買取センターという社名には、人々の不満をマーケティングにつなげようとする前向き感がありましたが、テクノロジーの要素が伝わらない。エン・ジャパンの越智会長には、社名変更を含めた、AIベンチャーとしてのリブランディングをやらせてほしいと話をしました。エン・ジャパンにも活用できるHRTech領域のデータ活用やマーケティングに限らないテキストデータの活用が拡大していくなかで、不満買取センターという社名では難しいと考えたからです。
そこで、「インサイトテック」という社名にリブランディングしました。テクノロジーで本音・本質を洞察し、課題を浮かび上がらせたい、という想いを込めています。
ジョインしたときの「不満買取センター」という社名を聞いた時には、親戚一同、何をやっている会社はわからないけど大丈夫か、と考えたようですが、「私がやらなければいけない」という思いで入社しました。世界唯一であるがゆえに、ビジネスの難しさに挑戦したいと考えたのです。
真の意味でのマーケティングを実現できる場所
――ビジネスとして難しいと考えた理由を教えてください。
伊藤:現在のマーケティングは、生活者視点といいながら、経験に基づく仮説を検証していこうというモデルが多いです。一方で、不満買取センターが手掛けている、人々の不満から仮説を組み立てて、これを商品やサービスに反映してビジネスとして成立させていくようなモデルは、多くの企業のマーケティングのかたちを変えることになるからです。
マーケティングのかたちを変える必要がある難しさはありますが、不満買取センターこそ、真の意味での生活者視点のマーケティングを実現できる場所と感じたのも事実です。誰が買ったか、誰が買いそうか、ということが数字だけで語られることが多い昨今、本当にこれだけでお客様本位のマーケティングができるか、という問題意識もあり、その難しさに挑戦したいと決意しました。
――インサイトテックが他社と異なる点は。
伊藤:競合する企業がないため、企画コンペになるケースがありません。「やる」「やらない」で決まることが大半です。データのストックに加えて、技術的な側面でも、日本語の主語や述語の関係や文章のエッセンスを抽出するAIを持っていることに優位性があります。これらを兼ね備え、商用化しているのは、当社だけなのです。
これができるのは、産学連携をしているからです。自然言語処理の第一人者である京都大学の黒橋禎夫教授と連携しています。インサイトテックのデータを提供をして、解析手法を先行的に使わせてもらっています。
チームのメンバーが多様なことも同業他社にはない点です。元々エン・ジャパンで採用コンサルティングに従事していたセールスや、広告代理店出身のリサーチャー、データサイエンティスト、UI/UXデザイナーの役割も果たすエンジニアなどが在籍しています。データサイエンティストは2名在籍していますが、1人は博士課程からの新卒で、エン・ジャパンに入社しました。私は、ブリッジとして彼らをつなぐ役割です。
――顧客の課題を解決するコンサルティングファームのような役割もあるのでしょうか。
伊藤:データと解析する手段という我々の武器で、お客様の課題を解決するという意味では、コンサルティングファームのようです。ですが、プロジェクト1件1件に人を貼りつけるようなスタイルは志向していません。お客様に寄せられるコメントを我々のAIで解析をして、具体的な課題や解決方法などをスピーディーにご提供します。

個性を尊重しつつも、何事も当事者意識強く
――インサイトテックのカルチャーを教えてください。
伊藤:多様性に富んでいることです。フラットな組織の中で多様な人材が相乗効果を発揮しながら活躍できるチームだと思います。組織の中にセクションを作ることはまったく志向していません。
実際、データを使って課題解決までつなげようとすると、全部1人でできるわけではありません。いろいろな人材が関わる必要がありますが、セクション化してしまうと、仕事の成否や遅れを誰かの責任にしてしまうからです。これは、顧客本位、課題解決本位ではないと思います。
事業成長が自分の成長ととらえる社員も多いです。ですので、何事も自分事として認識していて、当事者意識も強いです。個性を尊重しながら、大まかな方向性や根っこの部分を共有しているためだと思います。やれる人がやれることをやり切る。その中で正解を見つけていくスタイルがうまくいき始めていると感じます。
当社の事業の基軸である日本語データをより活用しやすい形にしていくことで、日本のビジネスを強くしていきたいです。日本語は文法や言い回しが英語と比べて難しく、データとして十分に活用されてないと感じます。我々がぜひ、ブレークスルーさせたいです。

いろいろな領域と関わり、成長できる人と働きたい
――一緒に働きたい人はどんな人ですか。
伊藤:仕事とプライベートを明確に分け過ぎない人です。仕事で成長できるとプライベートも充実して、結果として人生が豊かになると考えている人が向いていると思います。
また、「こういう役割で、プロとしてきました、以上」みたいな人は当社には向いてないと思います。単機能でのプロフェッショナリズムを追求しすぎず、「T字型」を志向できる人がよいと思います。「T字型」とは、深い専門性だけではなく、多様な領域をブリッジできるような人材のことを言います。自分が持っている専門性を、異なる領域に横展開し、自分が変化するのを楽しめる人、いろいろな領域と関わり自分を軽やかに成長させていける人が、活躍できると考えています。
この記事を友達に教える





