会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
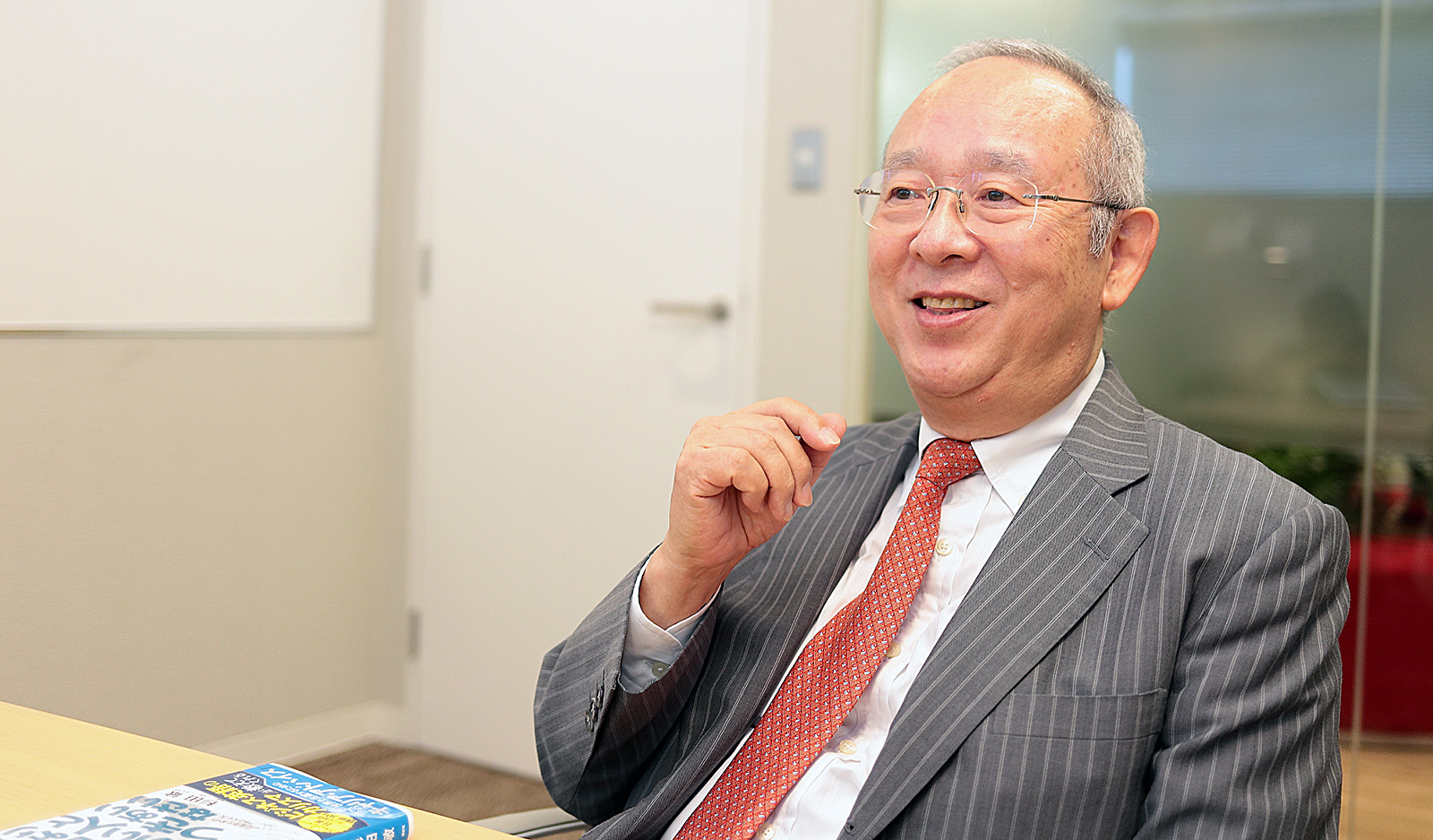
「成長したければ、自分より頭のいい人とつきあいなさい」。そんな刺激的なタイトルの本がこの夏、講談社から出版されました。副題は「グローバル人材になるための99のアドバイス」。著者は、NHKラジオ「実践ビジネス英語」の講師で、外資系PRコンサルティング会社・バーソン・マーステラ(ジャパン)の社長や日本ゼネラル・エレクトリック(GE)の副社長を務めた経験をもつ杉田敏(さとし)さんです。いくつもの外資系企業で働いてきた杉田さんにインタビューし、外資系企業の内情や社員に必要な心構えについて聞きました。(取材・構成:亀松太郎、撮影:土井大輔)
外資系は「辞表」を丁寧に書く
――杉田さんの本の中で印象的だったのは、辞表の書き方について詳しく説明していた点です。外資系企業というとドライなイメージがあるのですが、杉田さんが転職の際にとても丁寧な辞表を書いていたと知り、驚きました。
杉田:日本だったら、退職の理由を「一身上の都合」と一言だけ書くことが多いでしょう。でも、外資系だともっと丁寧なんですよ。決まった辞表の書き方があるわけではないですが、退社日と上司や会社に対する感謝の気持ちをどこかに盛り込むのが通例です。また、上司に突然、辞表を持っていったらダメです。最初は口頭で話をして、その後に正式に辞表の形で出すわけです。
――外資系は転職が多いからこそ、辞表の書き方は重要ですよね。では、転職などで新しい会社に入るとき、注意すべきポイントはなんでしょうか?
杉田:会社のカルチャーを把握しておくことがすごく大事ですね。その人にどんなに力があっても、カルチャーが合わないと成果は出せない。前の会社の社風が新しい会社では通用しないこともあります。たとえば、夜遅くまで働いた次の日も、いつもと同じように定時に出勤しないといけない会社もあれば、多少遅れても問題ない会社もあります。情に厚い会社もあれば、その逆もある。
――外資系と一口に言っても、会社によってカルチャーが違うということですね。
杉田:私が副社長を務めた日本GEは、はっきりしたカルチャーがありました。「力があれば上にいく。なければ辞めてもらう」。いわゆる「アップ・オア・アウト」ですね。部長以上のクラスで入ってくる人には、最初にそう言っていました。それを聞いて怖気づいてしまって、入社をやめた人もいた。逆に、そういうカルチャーが合う人は、入社後に成功していきました。
――会社のカルチャーは外からわかりにくいものです。就活生はどうやって調べればいいでしょう?
杉田:まず、インターネットで情報を集めることでしょう。英語で検索することができれば、より多くの情報が収集できます。そして、面接でしっかり質問をすることが大事です。ただ単に面接官の言うことを聞いているだけではダメですね。
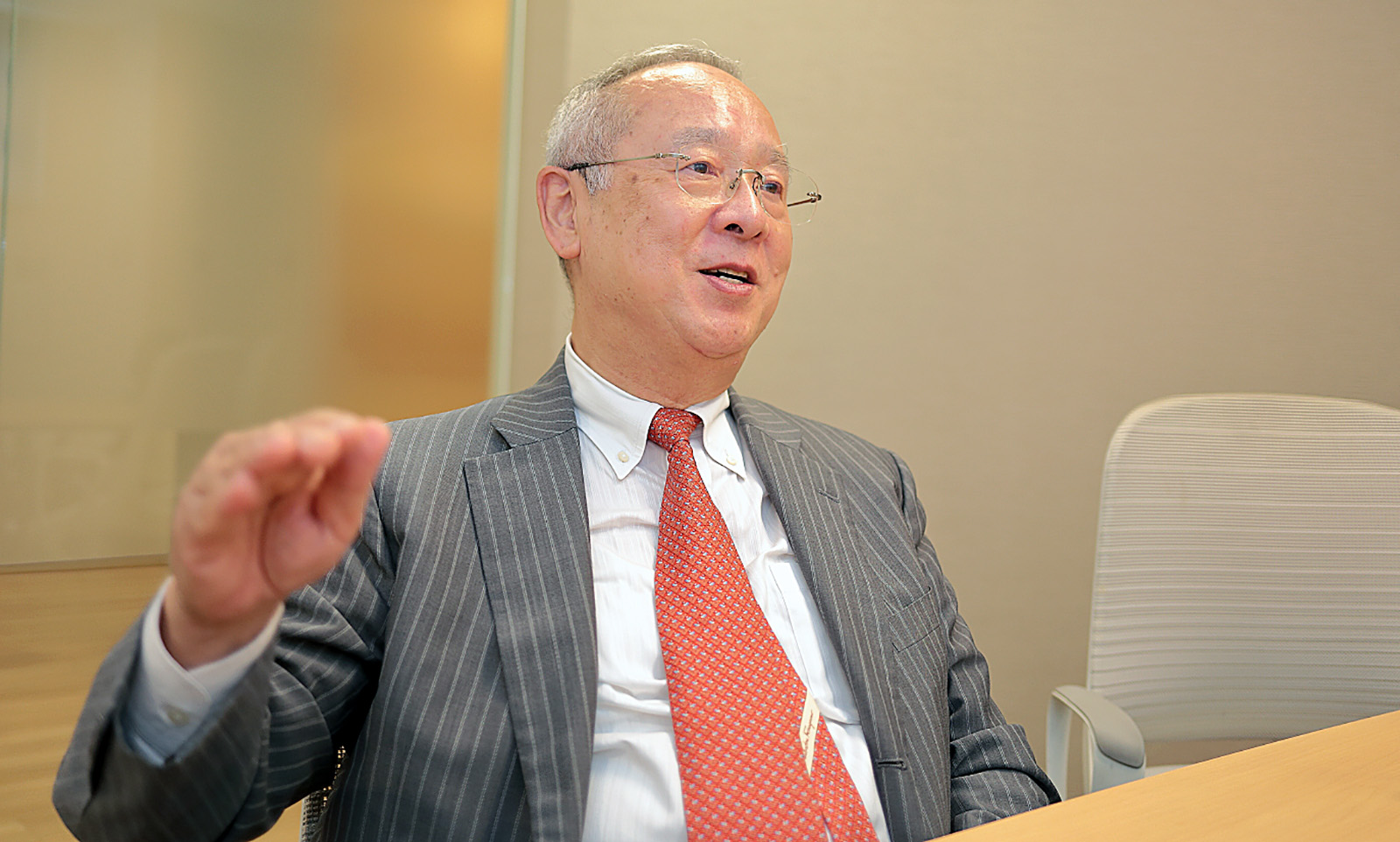
「会社を辞める」のは悪いことではない
――さきほど「アップ・オア・アウト」の話がありましたが、外資系企業の社員は一般的に、早い成長スピードが求められるとのことですね。
杉田:私はプラップジャパンで社長をしているとき、新入社員に向かって「この会社に3年いて上司がバカに見えなければ、あなたは進歩していないかもしれない」と話していました。管理職からはひんしゅくを買っていたかもしれませんが、本当にそう思っていたんですよ。一日でも早くプロフェッショナルになってほしい。会社としては、10年も20年も待っていられないんですね。
――短期間で「上司がバカに見える」ほどのレベルになるには、どうしたらいいんでしょう?
杉田:自分なりの目標を立てて、そのプランを実行することが大事です。入社して1年後、2年後に、自分は何ができるようになっていたいかを考える。私は転職を何回かしたけれど、いつも期間を決めて目標を立てて、それに向かって努力することを心がけていました。
――具体的には、どういう目標を立てていたのでしょう?
杉田:私が最初にPR会社に入ったときは「1年で企画書をきちんと書けるようになる」のが一つの目標でした。一人前の企画書を書けるようになるのに、数年かかる人もいますから。ほかにも「クライアントとの会話をスムーズにリードできるようになる」とか、「プレゼンをして新規の顧客をこれだけ取る」など、いろいろな目標が考えられるでしょう。それに基づいて、自分が成長していくのが重要です。
――目標を立てて成長していくことは、いい転職をするためにも大切ですね。
杉田:アメリカのPR会社では、新入社員は3年ぐらいで転職する人が多いですね。65歳の定年まで一つの会社で働こうなんて、考えている人はほとんどいません。会社を辞めることは悪いことではないんです。
――退職に対して、ネガティブなイメージがあまりないんですね。
杉田:なかには、いったん辞めたあと、いろんな経験をして成長して、また元の会社に戻ってくる人もいます。私自身、日本GEの副社長を務めたあと、前職のPR会社バーソン・マーステラに戻って、日本の現地法人の社長をすることになりました。

怖い上司に向けて放った「捨て身のジョーク」
――外資系企業は、社内のコミュニケーションの取り方が日本企業と違うのではないかと思います。そのあたりは、どう考えたらいいでしょうか。
杉田:私は基本的に、正直にコミュニケーションをするのがいいと思っています。昔、ある会社にいたとき、アメリカ人の上司がとても怖い人だった。同僚もみな怖がって、あまりそばに近寄らなかったんですが、ある日を境にその人との人間関係が劇的に好転しました。
――何があったのですか?
杉田:ある日、その上司が出社したとき、首からティッシュペーパーがコヨリのようにぶら下がっていたんですね。どうやら髭を剃ったときに少し切ってしまって血を止めていたようなのですが、そのティッシュがみっともない状態になっていました。「これは言ってあげたほうがいいかな」と思いましたが、やっぱり怖いんですよ。
どうしようかと考えて、「まずはユーモアで接するのがいいかな」と。そこで、彼に向かって「今朝、自殺を試みたのですか?」と言ったんですよ(笑)。そしたら「Why?」と、すごく怖い表情で聞き返してきました。「いや、だって血止めをしたあとのコヨリみたいなものがぶら下がっているので」と言ったら、「ええっ、こんなみっともない姿だったのか!」と気付いてくれました。
――なるほど、捨て身のジョークですね。
杉田:その上司は「今朝、あなたに会う前に3人の社員と会ったけれど、誰も何も言ってくれなかった。ストレートに指摘してくれてありがとう」と言ってくれました。その後、3人のところに1人ずつ行って、「なんで、あなた何もは言わなかったんだ!」と怒鳴っていましたよ(笑)。私以外の人はみな怖くて、何も言わなかったんですよね。それ以来、彼と私の関係はすごく良くなりました。「私のことを思いやって、ちゃんと醜態を指摘してくれた」と感謝してくれたんですね。
――杉田さんの本の中でも「ユーモアの大切さ」に触れていますね。
杉田:ユーモアは重要です。ただ、その場にあったユーモアでないといけません。日本とアメリカだと感覚が違いますし。たとえば、会議の席上、日本人が小さい声でボソボソと発言していると、アメリカ人が「もっと小さな声でしゃべってください」と言ったりします。すると、その日本人はますます小さい声で話してしまって(笑)。もっと大きな声で、ということをユーモアで伝えているのに、それが理解できていないんですね。

――かつてに比べると、外資系企業で働きたいという学生は多くなりました。そんな学生に向けて、アドバイスをいただけますか。
杉田:どういう業界を目指すにしても、自分の得意なことを生かせる会社に入るのがいいでしょう。ただ単に、ある会社に入りたいというのではなく、その会社で何をしたいかを具体的には考えてみる。たとえば、P&Gの場合は「マーケティングをやりたいから入社する」という人が多いですよね。P&Gのマーケティングは有名で、優秀な人が多くて、研修制度もしっかりしているからです。その会社で自分は何をしたいのか。自分の特徴が生かせるのか。それをしっかり考えて、就活をするのがいいと思います。
会員登録すると
このコラムを保存して
いつでも見返せます
マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事
P&G アクセンチュア
内定攻略 会員限定公開
トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム
この記事を友達に教える



