
マスコミ就活の全貌と今やるべきこと【出版編】
2025/03/13
会員登録すると
このコラムを保存して、いつでも見返せます
こんにちは、外資就活 マスコミ・広告チームです。
今回はマスコミの中でも出版社の就活に迫ります。出版社というと倍率が高そう、実際どんなことをしているの? とわからないことも多いはず。そこで今回は出版社はどんな試験を行っているのか、どう対策をすればいいのかをご紹介します!
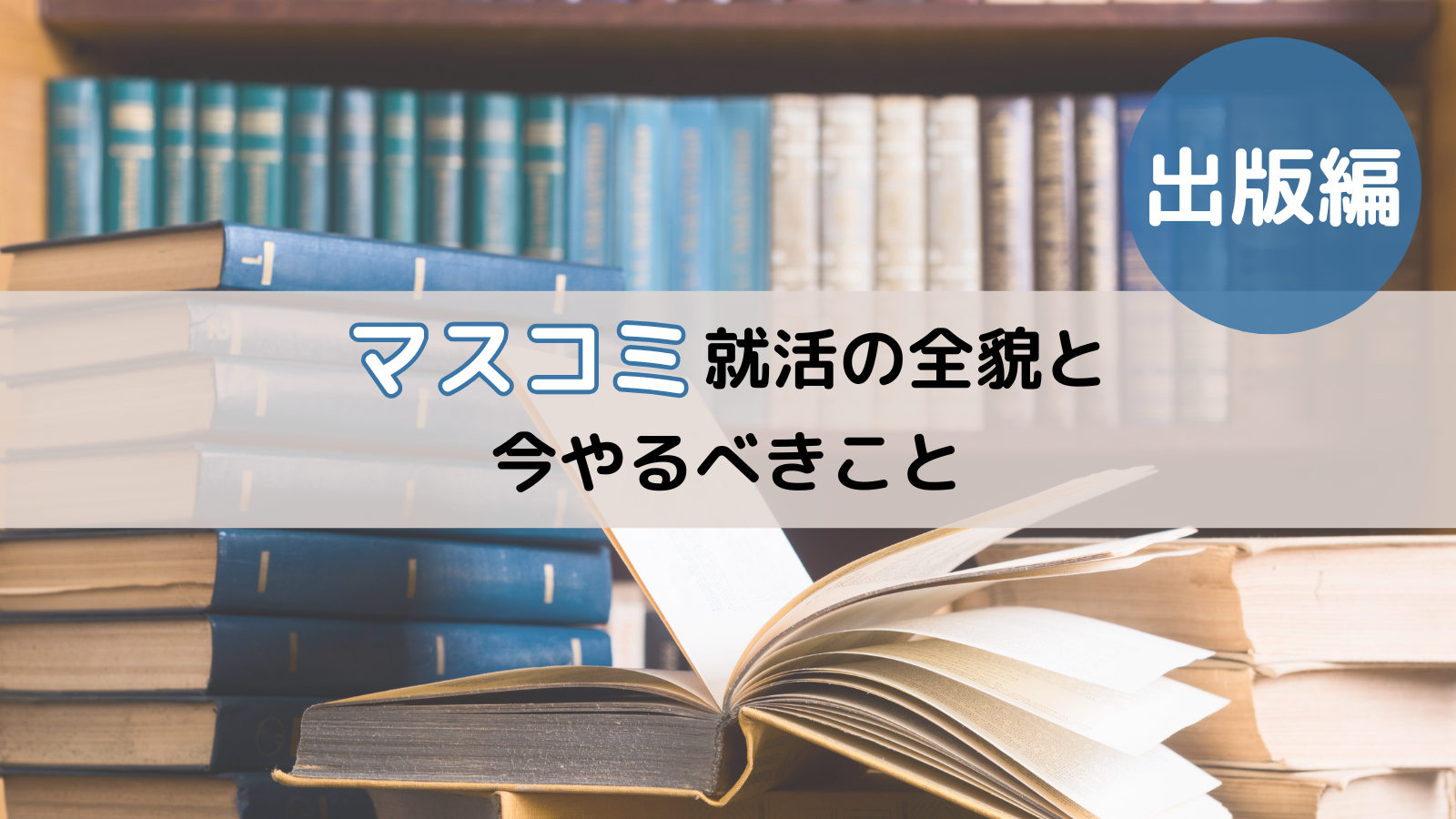
出版社の選考フロー
今回は大手出版社5社(講談社、小学館、集英社、新潮社、文芸春秋)に注目します。大手出版社は主に2月にES解禁、4月には締め切ります。ここで注意していただきたいのが、中堅出版です。中堅出版や専門出版は自社のホームページで募集を行い、3月にはESを締め切ってしまうところもあります。また新卒で採用を行っていないところ、人が足りなくなった時だけ募集するところも多いです。自分が興味のある出版社の情報については常にアンテナを張っておきましょう。
ここでは大手5社の選考フローおよび採用人数を見ていきます。編集、校閲、営業と様々な部署がありますが、採用はほぼ同じです。
書類審査 エントリーシート
筆記試験 適性検査とテストセンター
1次審査 個人面接
2次審査 個人面接
3次審査 個人面接
4次審査 個人面談(人事面談)
5次審査 個人(役員)面接
採用人数:26人(25卒)
書類審査 エントリーシート
筆記試験 Webテスト
1次審査 個人面接
2次審査 個人面接・筆記試験(三大噺、クリエイティブテスト、要約)
3次審査 個人面接
4次審査 個人面接
5次審査 集団面接、個人面接
採用人数:17人(25卒)
書類審査 エントリーシート
筆記試験 一般常識、漢字、英語、三題噺
1次審査 個人面接
2次審査 個人面接2回・集団面接
3次審査 個人面接
4次審査 個人面接2回
5次審査 集団面接
採用人数:19人(25卒)
書類審査 エントリーシート
筆記試験 一般常識、作文
1次審査 個人面接
2次審査 個人面接
3次審査 個人面接・集団討論
4次審査 個人(役員)面接
採用人数:5人(25卒)
書類審査 エントリーシート
筆記試験 一般常識、英語、人物説明
1次審査 個人面接
2次審査 個人面接
3次審査 個人面接・筆記試験(一般常識、作文)
4次審査 個人面接
採用人数:5人(25卒)
ここまで見ていただいて出版社就活の特徴は以下3つであることが分かるかと思います。
1.面接が多い
2.筆記試験が特徴的
3.採用人数が少ない
1に関しては様々な角度で人となりが見られています。面接は個人で30分に及ぶことも多く、予想外の質問も多いです。最終面接が近くなると面接官7人と行うことも。
2は筆記試験が複数回行われたり、いろんな問題で長時間行われるということです。クリエイティブ作文や三題噺などオチがあるストーリー作成が求められます。
3は各社の採用人数を見れば一目瞭然でしょう。マスコミ業界は1社あたりの採用人数が少ないですが、 大手出版社は特に少ない 部類に入ります。大手広告の電通や博報堂は100人~150人程度毎年採用していますし、大手新聞社の朝日・読売・日経も各社50名程度を毎年採用しています。それに比べると、出版社の採用人数の少なさが分かるでしょう。
3年生の夏~冬
では具体的に何をやればいいか、逆算して考えましょう。まず時間のある3年生の夏。周りと差別化をするためにどうしたらいいでしょう。
好きな本を読む(ノートをつける)
出版社志望にとって企業研究、企画作りが大切です。そこで後々のES、面接対策に向けて読んだ出版物の感想をノートに書き留めておくことをおすすめします。まずは好きなジャンルから始めるのがとっつきやすいでしょう。自分はどんなところが好きなのか、自分ならどんな企画を作るか、出版物の改善できるところなど、感じたことを書き留めましょう。出版社で働くイメージをそこから膨らませるとよいでしょう。面接の際に「働くイメージが具体的にできている」とアピールすることにもつながります。
またもし漫画が好きなら、普段自分が読まないジャンルの漫画にも手を広げることをおすすめします。例えば講談社の場合、漫画誌だけでも月に20誌ほど発行されています。直前では比較する時間が取れないものです。今の時期に好きなものに惜しみなく時間を使いましょう。
筆記試験対策を始める
出版社はマスコミの中でも特に筆記試験が特徴的です。新聞社は時事問題ばかりですが、出版社は時事問題に漢字、エンタメ知識に料理やファッション、スポーツの問題ととにかく幅が広いです。変わった問題も多いですが、時事問題や漢字など基本的なところをカバーするだけでも周りと差をつけられます。この時期から新聞やテレビを見たり、マスコミ漢字を対策しましょう。内定者もテレビを見ながらエンタメ系のニュースをノートにまとめていたといいます。
またSPIやGAB問題など一般的な就活の筆記試験も出題されます。ついつい対策し忘れてしまうので気をつけましょう。
出版社の長期インターン
出版社で気をつけていただきたいのがインターンの扱いです。出版社はテレビや新聞、広告業界のようにインターンをあまり行いません。実際、26卒では講談社のみが複数日程開催のインターンを実施し、小学館、集英社では複数日程開催のインターンは行われませんでした。つまり大手出版社でのインターンルートという早期選考はありません。
しかし一方で編集者の仕事がわかりにくいという面もあります。そこで早期に編集者になりたいという学生におすすめしたいのが、出版社の長期インターンに参加することです。新潮社では8月くらいから1カ月ほど長期インターンを募集しています。また、KADOKAWAでは大学1年生からが対象の長期インターンの募集にもあります。これら以外にも中堅出版では自社ホームページや雑誌の誌面で編集アシスタントを募集していることがあります。自身の経験値になるだけでなく、インターンからの採用を行っているという話も。本当に働きたいのなら、応募しましょう。
出版系のイベントに参加する
周りに編集者志望がいない、何をしていいかわからないという人におすすめなのが出版系のイベントに参加することです。例えば『マスコミ就職読本』では志望ジャンル別のメルマガの登録も行っています。私自身も出版社志望のメルマガに登録し、会社訪問のお知らせや読むといいコラムなどが定期的に流れていました。
また出版社で働いている社会人や志望している就活生で構成されている「T.O.P&M」という団体もイベントを行っています。ここでは実際にES添削や模擬面接も行っており、周りに出版社で働く知り合いがいない! という学生におすすめです。
3年生の冬~3月
国会図書館に通う
出版志望者が必ず通うのが国会図書館。ここには今まで刊行された出版物が保管されているので、雑誌などのバックナンバーも読み放題です。実際、就活間近になると多くの就活生が志望する出版社の刊行物を読んでおり、「あの人は〇〇(出版社)を受けるのか・・・」とわかるほどです。また特におすすめしたいのが単行本ではなく雑誌で読むことです。
例えば漫画だと編集者のコメントが載っていたり、雑誌ごとにカラーがあります。実際、受験生が面接で「〇〇(漫画誌)での企画ある?」と5誌もの企画を聞かれたという声も。これは漫画誌でもそれぞれのターゲットやジャンル、雰囲気をつかんでいないと答えられない質問です。すぐに身につくものではないので、早めに始めましょう。
またどれくらい読み込むかの目安ですが、志望ジャンルの雑誌は最低1年分、その他も3ヶ月分は読んでおきましょう。さらに受けない会社でも他社比較をするために読まなくてはいけません。時間がかかる作業なので早めにやっておきましょう。
OB・OG訪問をする
この時期に始めていたいのがOB・OG訪問です。編集者の方がどんな仕事をしているのか知るきっかけにもなりますし、ESを見てもらいましょう。出版社のESはクセが強いからこそ、業界の人に受けるものとウケないものがあります。採用人数が少ないからこそ、OB・OG訪問で生の情報を仕入れてライバルに差をつけましょう。
例えば学生時代に頑張ったことも一般企業のような真面目なことを書くと、面白くないと言われることも。好きな本や、インタビューしたい人も普通すぎるや、逆にマニアックすぎてあなたが聞きたいだけでしょ? と厳しい意見もあります。複数人の方に見てもらうとテクニックがわかったり、興味を引くところ、引かないところがよくわかります。
さらに業界の裏側も聞けるのがOB訪問のいいところです。出版業界は電子化やメディア化など色んなことに事業を展開しています。自分1人で情報収集するには追い付けないところも沢山あります。そこで業界の第一線で活躍している人と話すと、最近こんなコラボがあったんだよね、今電子化進んでてという裏話も聞けます。
ES解禁
インターンがない分、2月になるとESが公開されます。締め切りは4月ごろなので2カ月も余裕があると思いがちですが、出版社のESは手書き4枚程度、しかも作文がつくことがほとんどです。ESの中身はやりたい仕事を具体的に、好きな本、最近関心のあること、大学生活であらすじを作って、自分が大人になったと感じるときや一発芸など多岐に及びます。初めて見ると何を書けばいいの? と思ってしまう質問ばかりなので早めに取り掛かりましょう。
ESでの注意点はネタをちりばめることです。好きなもの、やってきたこと、語れることは10個ほど分散させましょう。また企画はより具体的に書きます。例えば「この作家さんにこんなストーリーを書いてほしい」といった大きいことを書きましょう。ここで抽象的だと本当にやりたいのかも分からないですし、個性が出ません。現実的には不可能かもしれないと思うことでも、より具体的な大きなことを書いていい場です。
説明会スタート
ESの解禁と共に始まるのが説明会です。出版社の多くは自社の説明会を開催しています。抽選によるものも多いですが、自分の志望部署に近い編集者に話を聞くことができるのでぜひ参加しましょう。また人事の方や内定者との交流もあり、ESが解禁したからこその悩みを相談することもできます。説明会には出版物も置いてあり、それを見るだけでも、今売り出しているものがわかってきます。出版社は大学での企業説明会も行っていますが、現役の編集者に会える機会は自社説明会のみです。この時期を逃してしまうと聞けないので、申し込み忘れがないようにしましょう。
4年生~就活終わりまで
筆記試験
ESが通過すると次に待ち受けるのが筆記試験です。出版社の筆記試験はES通過報告の1週間後に行われたりと時間がありません。また筆記試験の時間は半日に及んだりと長時間で、平均点が半分にも満たないほど難易度も高いです。直前の対策としてオススメしたいのが受ける会社の出版物と文学賞をチェックしておくことです。どこの出版社も自社の売れた本に関する問題は出題されます。
例えば主人公の名前や台詞の穴埋め、実写化したらキャストは誰かなど。なかなか読む時間はないかもしれませんが、ストーリーはざっと押さえておきましょう。書店にいけば各社が売り出している本も分かります。タイトルや作者などメモしてくことをオススメします。また数年分の芥川賞・直木賞作品は問われます。作者名は漢字で書けるようにしておいたほうが良いでしょう。
模擬面接
5月になると面接が始まります。出版社の面接は個人面接であることがほとんどです。しかも1次面接から現役の編集者です。大体は自分の志望ジャンルに近い編集者が面接をするので、話が合うと盛り上がる分、生半可な知識では太刀打ちできません。
そこで模擬面接を行い、練習すると良いでしょう。出版社の面接では必ず企画が問われます。どこで何をやりたいのかを具体的にします。文庫や漫画なら誰にどんなストーリーで書いてもらうか。雑誌ならどんな企画をするか、今までの企業研究を参考にして、それまでにないものを考えましょう。またこれまでの本とのかかわりかたも必ず聞かれます。小さいときにどんな本を読んでいたのか、最近読んだ本は何かなどは答えられるようにしましょう。最近読んだ本は1冊にとどまらないことも多いです。5冊くらいは用意しておき、感想も含めて用意しましょう。
面接での注意点
面接で気をつけなくてはいけないのはなぜ出版社に入りたいかというのを、ただ本が好きではいけないということです。本が好きなら読者でもいいのではないかと言われてしまいます。なぜ作る側に回りたいのかというのは個性がでるポイントです。本を通して自分がどうなったのか、だから自分はこういう作品を作りたいなど一人一人あると思います。そこを突き詰めていきましょう。
さらに売れている作品はなぜ売れているのかを分析することをオススメします。そこから企画を考えることも出来ますし、読者のニーズをつかむことが出来ます。各社で大事にしていることなども見えてくるので、どこが良いのかを言語化してみましょう。
また私が面接を受けていて感じたことは、出版社は個を見てくれる会社ということです。他の一般企業だと真面目な話をしなきゃと思いがちですが、出版社はどんなエピソードもその人の個性としてくれます。個人面接で長時間に及びますが、色んな面をアピールできる場と考えると良いと思います。
本を読むことが就活
出版社の就活は大変と思うかもしれませんが、本に関われたり、自分らしさを出して面接出来たりと、良い面もあります。本気で目指すのなら早めに対策を始めましょう。出版物を読むという作業が一番時間がかかります。しかし時間をかければかけるほど企業研究だけでなく、志望動機作り、面接対策にも繋がります。就活中でも好きなものに惜しみなく時間をつかえるのがマスコミ就活の良いところです。
会員登録すると
このコラムを保存して
いつでも見返せます
マッキンゼー ゴールドマン 三菱商事
P&G アクセンチュア
内定攻略 会員限定公開
トップ企業内定者が利用する外資就活ドットコム
この記事を友達に教える


